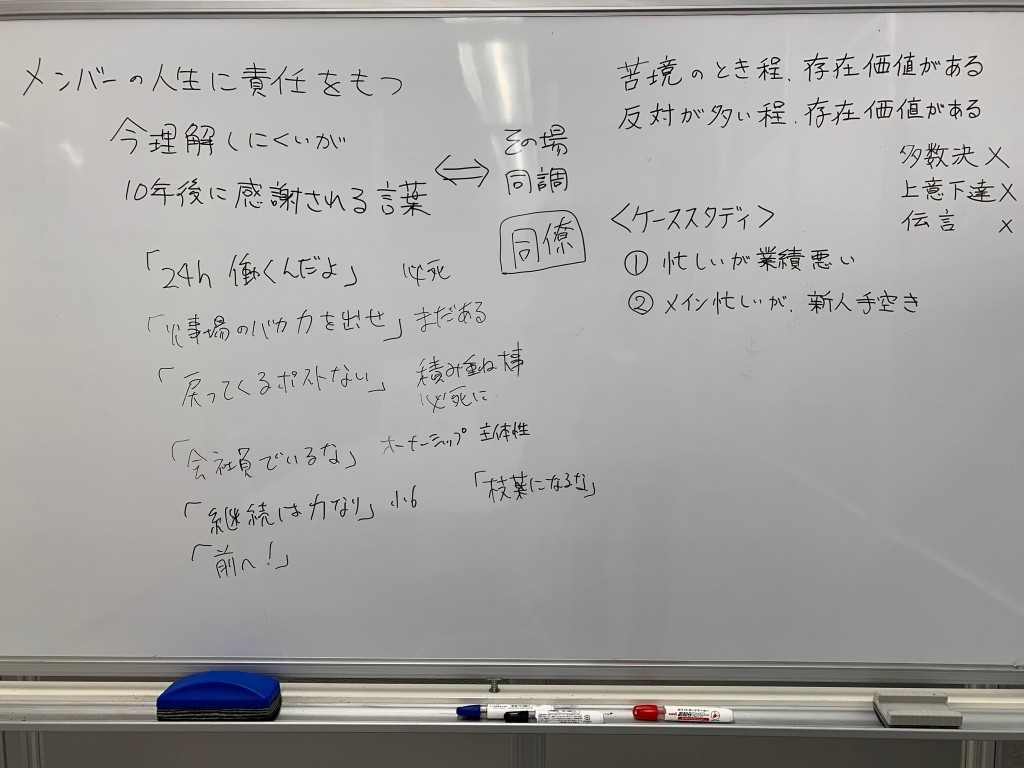こんにちは。
秋葉原オフィスの汲です。
仕事中の皆様は、
やることがいっぱいでなかなか終わらない、
仕事が思い通りにすすまない、
悩んでいませんか。
ここで、
例をあげながら、
仕事を早く片付ける方法を共有します。
✖入力を速くする
〇入力をなくす
→コピペする。
パソコンの入力システムを活用し、よく使う単語等を事前に登録して使ってみるとか。
✖メールを忙しくない時に返信
〇開いたらすぐに返信
→そして、メールをチェックする時間も決めましょう。
例えば、
・出勤してからすぐ一回
・お昼休みから帰ってきたら一回
・午後2時半ごろ一回
・午後5時半に一回
とか。
こうすれば、
手元の仕事に集中することもできるし、
メールのチェックと返信が遅れることを避けられます。
✖難しいタスクから取り組む
〇緊急度等がほぼ同じであれば、簡単なものから取り組む
→とにかくタスクを減らす作戦です。
「やらなきゃ」と思っていること自体がストレスになるからです。
簡単なものから取り組めば、
一つのタスクが消えるので、気持ちもすっきりし、
自然にそのままリズムよく次のタスクに移ることができるからです。
✖文書を一から書く
〇文章を枠から考える
→文章の構成を考えて、全体像をイメージしてから、
着手しやすくなる。
理由書も事業計画書も同じです。
✖今日は早く帰らなきゃ
〇定時に帰るために、今日はどうすればいい
→朝出勤する前に、もう一度一日の目標とタスクを整理し、
定時退社をするために、
何時までに何を完成すればよいのかをしっかり考える。
✖他人が決めた期限に合わせて仕事をする
〇自分で期限を決めて行動する
→主体性をもって、
前をもって動きましょう。
皆様が仕事を進んでいる中、
「こうすればもっと効率よく仕事できる」と気づく機会も非常に多いかと思います。
気づいたことを日報に書いたり、
共有メールで流してみたり、
どんどん発信していきましょう。
皆さんの努力は会社の成長にもつながるので、
一緒によりよい会社を作っていきましょう。
今週も三連休なので、
気持ちよく休みに入られるように、
今からいろいろ取り組んでいきましょう。
それでは今日も元気よく楽しく頑張りましょう。