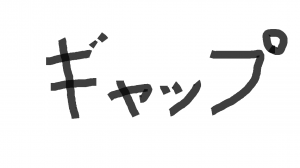こんにちは。秋葉原支店の清水です。
今回は、ボトルネックを解決しようって話です。
マネジメントでは、ボトルネックの解決は大切です。
ボトルネックとは「仕事の足止めになる工程」のこと。
例えば当社で請け負っている「入札参加資格申請代行」の
業務で言うと、書類作成と納品(申請)は進んでるけど
ダブルチェックが溜まっている時は、ダブルチェックを
ボトルネックと言って、下記のようになります。
入札案件の過去事例① アクション前
ーーーーーーーーーーーーーー
作成件数:20件/週
↓
ダブルチェック件数:5件/週
↓
納品(申請)件数:15件/週
ーーーーーーーーーーーーーー
この事例ではダブルチェックが滞っているから、
作成や納品(申請)の担当者がいくら頑張っても、
全体としてはどんどん遅れていきます。
そのため、ここで管理担当が打たなくてはいけない手は、
作成担当にダブルチェックをしてもらうなど、
ダブルチェックを速めることなんです。
入札案件の過去事例① アクション後
ーーーーーーーーーーーーーー
作成件数:15件/週
↓
ダブルチェック件数:15件/週
↓
納品(申請)件数:15件/週
ーーーーーーーーーーーーーー
これでひとまず解決です。ところが、安心はできません。
ボトルネックは常に変わるため、管理担当は常に状況を把握し、
ボトルネックを探し、解決策を打つことになります。
上記の事例では、2週間後にこうなったりします。
入札案件の過去事例② アクション前
ーーーーーーーーーーーーーー
作成件数:15件/週
↓
ダブルチェック件数:15件/週
↓
納品(申請)件数:0件/週
ーーーーーーーーーーーーーー
納品(申請)の担当者が体調を崩してしまい、
会社で来れなくなった、というケースです。
こうなってしまったら、これまではマネジメント
だけだった管理担当が納品(申請)に入るなどして、
急場を凌がなくてはなりません。
入札案件の過去事例② アクション後
ーーーーーーーーーーーーーー
作成件数:15件/週
↓
ダブルチェック件数:15件/週
↓
納品(申請)件数:13件/週
ーーーーーーーーーーーーーー
この間に納品(申請)の担当者が戻るなら良し、
長期で離脱するなら慣れた人を入れたりして、
ボトルネックである納品(申請)を解決するっていう流れです。
ちなみに、1つのアクションは別の事象を生むため、
それも想定して動くとベストです。上記の事例で、
管理担当が納品(申請)で忙しいとマネジメントが
疎かになり、別の場所でのボトルネックが発生しそうです。
そのため「管理担当の別業務で、簡単に任せられるもの」
を誰かに任せるなどして、手を空けておくこともリスク
ヘッジとしてあり得ます。
このように、マネジメントでは、常に状況を把握し、
ボトルネックを探し、解決するというプロセスを繰り返す
ことになります。
今回は進行件数に限ったことですが、実際はチームメンバー
(欠員含む)、業務フロー、顧客がボトルネックになることも
あるので、まあ大変といえば大変ですが、やってやれないことは
ないので、みなさん、頑張って行きましょう!


 こんにちは!新宿の近藤です。
こんにちは!新宿の近藤です。