鈴木です。
昨日、社外の女性活躍プロジェクトの研究会に参加しましたので、学びを共有します。
・一般的に、多様性があることは、ネガティブな要因になりうる。
・同質的な集団のほうが、まとまりがよく、パフォーマンスが良い。
・多様性重視の風土がある職場の場合にのみ、多様性はプラスの効果を生む。
多様性は、パフォーマンスが高くなると思い込んでいたが、
それは、多様性重視する雰囲気があったため、それがプラスに働いていただけと認識を改めた。
多様性重視の風土を維持し、さらに強化していくに注力したい。
・組織風土とは、「他の人の考えの推測」によって構成されている。
・特に、身近な上司や同僚の発言を組織風土として認識するので、
・そのように捉えられることを意識して、言動すべき。
・不用意な発言は、言ったほうは忘れているが、言われたほうは根に持つことが多い。
組織風土をどう作るのかというのが、テーマだったが、
それは、各人の発言によることが大きいことが分かった。
受け手側がどのように発言を認識し、そこからどのように社風を推測するのかを意識したい。
「同質的な組織の効率よりも、それぞれのメンバーが多様な価値観で活躍することを重視したい」と伝え続けたいと思った。
多様性を生かす道を考え続け、社内で活躍できる幅を広げていきたい。
投稿者: shigyo_user
ありのままでは足りない

ダイバーシティ経営に取り組むようになって、
多様な人材をどのように活用していくかを深く考えるようになりました。
周りの人をよく観察してみると、
人は本当に千差万別で、考え方も価値観も異なるんですね。
もっと標準みたいなのがあるかと思っていましたが、
標準的な人ってのは、どこにもいなくて、
みんな「変」だと分かりました。
以前、ダイバーシティのセミナーで、
「多様な人材がいてるだけではダメで、その人が活躍しているかが大事」
と教わりました。
その人をそのまま受け入れて、居場所を作ってみたいなことは、
そんなに難しくないけど、
その人に十分活躍してもらうことは、まだ自分の力では及ばない。
その人の特性を生かして進化してもらうには、
自分自身の進化も必要です。
自信を持たせる
 鈴木です。
鈴木です。以前、自信を持たせるには、「成功体験が必要だ」と信じていた。
何か結果を出したり、やり遂げた達成感を感じさせると、
その人に自信がつくように考えていた。
そして、そのようにサポートして、
いい結果に導いたり、最後まで頑張らせたりした。
ところが、予想に反して、自信はつかなかった。
いい結果だと褒める指導者の側には、
自分の成功と実感できずに、心の奥に複雑な気持ちをもって喜ぶ当人がいた。
最後までやりきったと称える周りに囲まれて、
自分ひとりではできなかったと照れながら喜ぶ当人がいた。
どちらもハッピーエンドのようで、
自信を持たせることにはマイナスな効果となった。
自信とは、「自分自身を信じる力」
もう一度、ゼロから深く考えるようになった。
子供の成長の軌跡が参考になった。
くつが履けた。
自転車に乗れた。
バタフライが泳げるようになった。
走りでクラス一番になった。
中学受験で頑張った。
英検で資格を取った。
ダンスで入賞した。
生徒会に立候補した。
子供にはいろいろなチャレンジの経験がある。
うまくいった場合もあるし、失敗となった場合もある。
自信をつくかどうかは、
何をして、どうなったかという結果ではなく、
どのように取り組んだかがポイントだと気づいた。
つまり、自分でしたことは自信を深めるが、
家族や他人にしてもらったことは、自信を喪失させる。
それは、結果の良し悪しに関係ない。
失敗に終わったとしても、自分で考え、自ら取り組んだ経験は、
自分はひとりで難しい課題にチャレンジできるんだという自信になり、
成功したとしても、誰かに手伝ってもらったことは、
自分はひとりでは成し遂げられないという自己否定感に繋がる。
そうすると、そもそも「自信を持たせる」とかってことは他人にはできないことで、
周りは、関与することで、自信を失わせる効果しか出せないのかもしれない。
きっと、自分を信じる力は、自分の心の奥から生まれてくるんですね。
ダンス競技会
鈴木です。
昨日は、子供たちと地元のダンス競技会に参加しました。
今回は、次女と初めてのペアで、Samba、Chachacha、Rumbaと踊りました。
区長杯というレベルの高いクラスに参戦しましたが、
思いのほかジャッジが評価してくれて、4位に入ることができました。
競技ダンスは2人でやるので、
どれだけ相手のことを想うかが大切です。
自分がこうしたいとか、こうしようと思ったとかが中心になるのではなく、
受け手側の相手の感じ方やそれに伴う動きがポイントになります。
相手のために、自分が動くというのが競技ダンスの本質で、
どれだけ相手主体で、
なおかつ自分主導で動けるかというのがミソですね。
これがやけに難しくて、常に意識していないと、
自分主体で、相手に主導して欲しいと考えるようになってしまう。
昨日は、自分としては最高のダンスができました。
まだまだ初心者の娘とのペアということもあり、
相手がどうすれば踊りやすいか、
どんなメッセージをダンスの中で伝えるのがいいのか、
考え続けました。
おかげで、ぐったり疲れましたが、
とてもすがすがしい疲労感でした。
観客や他の競技者からは、
「こんなダンスが見たかった」
「ふたりの雰囲気がすごく素敵だった」
「娘さんがすごく楽しそうだった」
などと声をかけていただき、
人生最高の1日になりました。
昨日は、子供たちと地元のダンス競技会に参加しました。
今回は、次女と初めてのペアで、Samba、Chachacha、Rumbaと踊りました。
区長杯というレベルの高いクラスに参戦しましたが、
思いのほかジャッジが評価してくれて、4位に入ることができました。
競技ダンスは2人でやるので、
どれだけ相手のことを想うかが大切です。
自分がこうしたいとか、こうしようと思ったとかが中心になるのではなく、
受け手側の相手の感じ方やそれに伴う動きがポイントになります。
相手のために、自分が動くというのが競技ダンスの本質で、
どれだけ相手主体で、
なおかつ自分主導で動けるかというのがミソですね。
これがやけに難しくて、常に意識していないと、
自分主体で、相手に主導して欲しいと考えるようになってしまう。
昨日は、自分としては最高のダンスができました。
まだまだ初心者の娘とのペアということもあり、
相手がどうすれば踊りやすいか、
どんなメッセージをダンスの中で伝えるのがいいのか、
考え続けました。
おかげで、ぐったり疲れましたが、
とてもすがすがしい疲労感でした。
観客や他の競技者からは、
「こんなダンスが見たかった」
「ふたりの雰囲気がすごく素敵だった」
「娘さんがすごく楽しそうだった」
などと声をかけていただき、
人生最高の1日になりました。
きついけど面白い
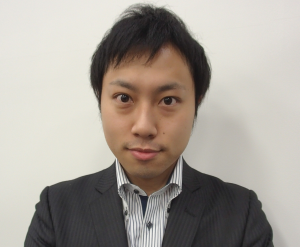
こんにちは!名取です。
大型の興行ビザが一段落つきました。
特に宮澤さん、王さん、協力してもらいありがとうございます。
『興行ビザ』これは私にとって唯一思い入れの深い業務です。
私が新人の頃、弊社に興行ビザの実績はありませんでした。
これを山田兄貴と共にマーケティングを図り、徐々に問い合わせ・ご相談が来るようになりました。
最初の一件目は無事に許可は下りたものの、内容的にはボロボロでした。
スピード、事前調査不足、段取りの弱さ、リスク対応の甘さ等が露呈し、かなり苦しみました。
興行という特性上、各タレントさんのイベントが決定してしまっており、しかもだいたいタイトなスケジュール。。クライアントからの間に合うか!?というプレッシャー。行政側の厳しい指摘!
それ以降も興行ビザを担当し、ノウハウも増えましたが毎回毎回、もう二度とやるもんか!と思います。笑
当時新人の私にとって先輩方が自分の持ち味を生かし、それぞれの分野で活躍する中で不甲斐なさも感じていました。
そんな中「興行 = 名取」というのが自分の存在価値であり、よりどころでもありました。
神経も使いますし、眠れない日もありますが、その分結果を達成したときの達成感はひとしおです。ニュースとかでも取り上げられることもありますので、直接的に自分の仕事を実感できます。
ビックイベントの場合、主催者、広告会社、プロダクション等、様々な企業が集合し一つのプロジェクトチームとして同じ方向を向いて進んでいきます。弊社はビザ専門家として参加しており、この点は我々にしかできない仕事です。
ビザ業務にかかわらず、許認可等でも思わぬビックネームとの遭遇もあり、
専門家としての位置づけでズバッと切り込んでいける醍醐味があります。
社内だけでなく、社外とのかかわりを持って仕事をするスケール感も味わえます。
比較的若い時期から、そういったことをがっつり経験できるのは
弊社での仕事で一番の魅力的だと私は思っていますし、それが楽しくてこの仕事を続けています。
子ども達との時間

これまでは遊び中心だったんですが、
子どもたちが大きくなるに従い、自然と勉強を見る時間が増えてきました。
受験があるわけでもないし、
いい大学に入って欲しいという想いが強いわけでもないのですが、
勉強を通して、教えておくべきことが多いことに気づきました。
知ることの楽しさ
できなかったことができるようになる喜び
自らのやる気を引き出す方法
効率的な時間の使い方と優先順位の決め方
目標設定とPDCAサイクル
自分の能力の客観的な把握と効果的な活用
まあ、たくさんあります。
勉強を教えるのに、知識や解き方だけを伝えるだけではもったいない。
子供に教えながら、親も一緒に育っていくって感じですね。
遊びを通して学ぶこと、勉強を通して学ぶこと、
これからも子ども達とできるだけ多くの時間を共有していきたいです。
勝因分析

仕事は上手くいく場合と上手くいかない場合がある。
上手くいかなかったときに、なぜ失敗したのかをしっかり考える。
ビジネス上では、一般的に「敗因分析」が行われている。
一方、勝因分析という手法もある。
上手くいったときに、その要因を分析し、反復性をもたせるやり方だ。
どちらも、改善を求めての手法になるが、
実際のビジネスでは、勝因分析のほうが、改善効果が高いように感じている。
勝因分析していくと、
当然のように成功したと思える事例にも、
スタッフの陰の努力があったり、見えにくいチームワークがあったり、
顧客との深い信頼関係があったりすることが分かってくる。
「○○さんの準備がよかった」
「はじめにしっかり打ち合わせして情報共有できた」
「いつも前向きな雰囲気を保てた」
「その場で役割分担を決めて、すぐに取り組めた」
そんな分析結果が次々とあがってくる。
仕事が上手くいく背景には、ちゃんと理由がある。
そして、その理由は、当然のように繰り返されるわけではなく、
ほとんどの場合、繰り返すことができずに、次回は失敗する。
だからこそ、何が成功の理由なのかをみんなで理解していくことは効果がある。
仕事ができる人とできない人の違い

この前、応募者の方からこんな質問を受けました。
「仕事ができる人とできない人の違いは何ですか?」
巷にはいろいろな答えがあるのですが、
私が最も重要と思うものは、
「仕事が多いと、嬉しいと感じるか、辛いと感じるかです。」
です。
仕事をやりがい、挑戦、楽しみ、などと捉えている人は、
業務量が増えると、喜びます。
自分のチャンスが増えるからです。
こういう視点で捉えている人は、仕事をしながらどんどん成長し、
その結果として、やがて「できる人」になっていきます。
対して、
仕事を義務、やらなければならないもの、面倒なもの、などと捉えている人は、
業務量が増えると、憂鬱になります。
周りの人よりも業務量が多いと、不満に感じます。
これでは、仕事を通して、成長することは難しく、
お金を稼ぐために、その仕事を捌くだけとなってしまいます。
知らないうちにどんどん差をつけられて、「できない人」に定着してしまいます。
まさに二極化してしまうわけですが、
お店の店員さんでもよく見かけられます。
お客が増えてきたら、イキイキして働く人と、嫌そうに働く人がいますね。
なぜ、こんなに仕事感が分かれてしまうんでしょうか。
社会に出たときのファーストキャリアが大きいように思います。
そのときに、仕事はこういうもんだ、と上司や先輩に叩き込まれます。
それが、「仕事はチャンスだ」と叩き込まれると、
どんな仕事も自分にとってチャンスだと感じ、どんどん挑戦していくようになります。
それが、「仕事は義務だ」と叩き込まれると、
義務は少ないほうがいいので、できるだけ自分の仕事を少なくし、楽することを目指し、
義務感を減らすようになります。
何事も初めが肝心と言いますが、
仕事のスタートにも当てはまります。
褒められたと感じる力
鈴木です。
長女がクラリネットにはまっています。
楽器をスタートしたばかりで、
なかなか周りの人についていくのが大変そうですが、
毎日、自室で練習に励んでいます。
先週、レッスン帰りの車のなかで、
「先生に褒められた!」とうれしそうに話してました。
じっくり聞いてみると、
譜面通りに演奏しているのを見ていた先生に
「そうそう」って言われただけ(笑)
でも、改めて考えてみると、
この褒められたっていう認識が、すごく大事なんじゃないかと思いました。
周りは、上手い人ばかりで、それを上回ることは当面なく、(これからもずっと?)
「素晴らしい!」なんて、言われる可能性はゼロです。
新人の今なら、「そうそう」って言われることが、
本人が得られる最大限の褒め言葉なんじゃないかな。
それをそのまま「褒め言葉」と認識すること。
毎回注意されてばかりいるなかで、
注意されるばかりで一度も褒められてないと感じるのと、
褒められることもあるって感じるのでは、これからの成長に差が出そうです。
「褒められたってほどでもないんやけど・・・」
って照れながら修正する娘に、
「それは先生が褒めてくれたんやで。よかったな」
って後押ししました。
長女がクラリネットにはまっています。
楽器をスタートしたばかりで、
なかなか周りの人についていくのが大変そうですが、
毎日、自室で練習に励んでいます。
先週、レッスン帰りの車のなかで、
「先生に褒められた!」とうれしそうに話してました。
じっくり聞いてみると、
譜面通りに演奏しているのを見ていた先生に
「そうそう」って言われただけ(笑)
でも、改めて考えてみると、
この褒められたっていう認識が、すごく大事なんじゃないかと思いました。
周りは、上手い人ばかりで、それを上回ることは当面なく、(これからもずっと?)
「素晴らしい!」なんて、言われる可能性はゼロです。
新人の今なら、「そうそう」って言われることが、
本人が得られる最大限の褒め言葉なんじゃないかな。
それをそのまま「褒め言葉」と認識すること。
毎回注意されてばかりいるなかで、
注意されるばかりで一度も褒められてないと感じるのと、
褒められることもあるって感じるのでは、これからの成長に差が出そうです。
「褒められたってほどでもないんやけど・・・」
って照れながら修正する娘に、
「それは先生が褒めてくれたんやで。よかったな」
って後押ししました。
難題への取り組みの試行錯誤

当社の経営理念のひとつに、
「常に難題にチャレンジし続けます」
があります。
今回は、その難題へのチャレンジの仕方について、
これまでの当社の試行錯誤をまとめたいと思います。
難題は、自分が解決策が思い浮かばないレベルの問題です。
だから、自分で少し考えたら、方向性が見えるような感じではないです。
マーケティングなどでは、経験者から見たら簡易な課題でも、
初心者にとっては難題ということもあります。
そんな難題に直面したときに、一般的に最も多いのが、
考え込んでしまうケースです。
「まず自分で考えろ」という一般常識に沿って、
PCの前で「う~ん」っと唸っているパターンです。
本人は考え続けているように思っているのですが、
途中経過を聞いたり、最終報告を受けたりすると、
ほとんどのケースで、堂々巡りしていたり、視野が狭くなってフリーズしてしまっています。
時間だけが浪費され、何も前に進んでいません。
そのため、当社では、従来より
「(自分で考えるのではなく、) まず最適者に聞け」
と教えてきました。
ところが、ここにも問題が出てきました。
「聞く」という行動が、情報を受け取る、指示を受ける、という風に認識されてしまい、
「どうしたらいいですか?」
「何から考えるべきですか?」
「ゴールは何ですか?」
とミッションを最適者に丸投げしてしまい、
自らがその下請け作業をするケースが目立ち始めました。
これは、私のメッセージが間違っていたと反省し、
メッセージをゼロから練り直しました。
「最適者に聞きながら、主体的に考えろ」
少し詳しく説明すると、
「最適者」とは、
上司、経験者等のなかで、課題を解決するのに最も適した人です。
最適者の選択を間違うと、解決は困難になります。
決して自分が聞きやすい人ではありませんので、注意が必要です。
なお、周りに最適者がいない場合には、本やネットの情報が最適者となることがあります。
「聞きながら」とは、
情報や指示を受け取り、それを参考にしながら、という意味です。
「主体的に考える」とは、
主体性を失わず、自分自身で考えるということです。
しかも、その場で考える必要があり、聞いてから、自席に戻って考えるわけではありません。

