東(アズマ)です。
プライベートでピアノを弾いているのですが、
仕事をしていると「ピアノの演奏と似ているな」と思うポイントがあるので、
3つ紹介します。
①顧客(聴衆)は「頑張り」を評価しない
「この人は10年もこの曲を練習したのだな、すごい」と思うこと(言われること)はあっても、
「この人は10年もこの曲を練習したのだな、良い演奏だ!」とはならないです。
(「すごい」と感心することと、「良かった……」と感動することは、
全く違うことです)
演奏を聞いて「良かった」と思うかどうかに、
その人がどれだけ練習をしていたのかは直接関係ありません。
(練習の結果、良くなった演奏を聞いて「良かった」と思うだけ)
また、
「たった3日の練習でこんなに弾けるのか、すごい」と思うこと(言われること)はあっても、
「たった3日の練習でこんなに弾けるのか、聴いて良かった!」とはならないです。
「たったこれだけの時間で」という情報は、
「その時間の割には、良く出来ている」程度の話です。
仕事でも、「これだけ頑張ったのだから……」「これしか時間がなかったから……」というのは、
何も関係ありませんね。
②自己評価には意味がない
自分で「良く弾けた!」と思っても、聴衆の心に響かないなら意味はありません。
逆に、「色々反省点のある演奏だった……」と思っても、
聴衆は良いと思ってくれるかもしれません。(滅多にないと思いますが)
アマチュアで自分のためだけに弾く分には、
自分の思う良し悪しだけで突き進むのも良いかもしれませんが、
プロでお金をもらうなら、そうはいかないでしょう。
(あくまで聴衆の評価が伴った上で、自分の最も良いと思うものを提供するでしょう)
仕事の場合、全員が顧客(や自分の会社)からお金をもらって働いている「プロ」なので、
顧客(や自分の会社)からの評価にこそ意味があります。
※仕事の場合、直接給料をもらっている以上、
自分の会社からの評価が大事とわかります。
ピアノの場合も、プロは聴衆から直接お金をもらうのではなく、
演奏会等の主催者・コーディネーターからお金をもらっている(ことが多いと思う)ので、
もしかすると聴衆以外からの評価も大事なのかもしれませんね。
(私はアマチュアなので、よくわかりませんが……)
③顧客(聴衆)の前では自信をもって振舞わなければいけない
人前で演奏するからには、
ステージに上がってからステージを降りるまで、
自信をもって(少なくとも自信があるように振舞って)いないといけません。
反省や修正・練習はステージの外でやるものです。
(プロでもアマでも)
間違っても、弾き終わった後などに、「いやぁ色々ミスしちゃったなあ……」などと
照れ笑いなどしてはいけません。
少なくとも私は、人の演奏を聞いた後にその素振りをされると、
(じゃあもっと練習してきなさいよ)と思います。
アマチュアでは、こうした仕草をする人が一定数います。
プロでは流石にそんな人居ないな、と長年思っていたのですが、
2021年のショパンコンクールの演奏を見ていた際、
まさにステージ上で「いやぁダメだったなぁ……」という素振りをする演奏者が居たので、
びっくりしました。
(当然というべきか、その演奏の審査の際に、その方は落選していました)
仕事でも、「いやぁすみません……」という態度の担当者と
一緒に業務を進めるのは、頼りないですし、
「この人にお金払って業務してるのか……」と思われてしまいます。
……ここまで書いたように、ピアノと仕事には色々な共通点があります。
これは恐らく、ピアノや仕事に限った話ではなくて、
何をしていても、大事なことは同じだからだと思います。
自分の興味のあること・やっていることを軸に掘り下げていくと、
他のことにも繋がっていくため、是非やってみてください。
投稿者: shigyo_user
オフィス対抗”とあるレース”
こんにちは新宿オフィスの土子です。
4月はオフィス対抗”とあるレース”が開催されました。
我ら新宿ウエスト(同フロアに2つオフィスがあります)は、
毎日のように「今どれくらい?あとどのくらいいけそう?」とオフィスを挙げて盛り上がっていました。
金商・不特チームでもサイトの毎日新ページUPを掲げて取り組みました。
「1位取れたらいいな」じゃなくて、「絶対1位」を目指して全力疾走し・・・
結果は・・・・2位。いやもう本当に悔しくて悔しくて悔しくて夢にも出てきました。
今回のレースは定例のものではなく、
新しい企画で4月限定開催だったので今後再開催があるかわかりません。
一度きりの戦いでした。
急に今回のレースが開催された背景は知らないですが、
きっと発案者の育成的狙いに乗ったと思います
この悔しさを糧により強いチームになります。
提案力・業務進行等々、レベルUPに繋がる発信を全員がします!
新人が評価されるには?
採用担当の榊原です。
採用面接で、「求めている人物像を教えてください」という質問
よくある質問ではないでしょうか。
サポート行政書士法人でも、求める人物像として以下の内容を掲げています。
【HPより抜粋】
・経営理念に共感できて、リーダーになる人
・自分のメリットよりも全体最適で行動できる人
・プロセスではなく、結果で評価を受けたい人
・ポジティブな人、チームワークが好きな人
・不満や愚痴を言わない人
・判断スピードが速い人
では入社後、新人が何をすべきなのでしょうか?
サポート行政書士法人に限らず、ルールはどの会社、組織にも存在します。
ただこのルールは、学校の校則などとは違い
仕事として、主体的に守ることが求められます。
ルールを率先して理解し実践することを徹底できれば、
どんな業界、業種でも、一目置かれる新人になることができるでしょう。
まずは「ルール通りに行動する」ことで周りをリードしてほしいと思います。
多くの会社では、「ビヘイビア」が評価項目となっています。
会社の理念、価値観を理解して率先して行動すること。
自他ともに対し、正直であること。
新人の皆さんは、心がけてみてください。
#行政書士 #採用 #コンサル #新卒

第一印象のその後は・・・?
こんにちは!
新宿本社の坂本です。
人間、第一印象って大事ですよね。
私たちコンサルタントでは特に大切だと思います。
清潔感だったり、信頼できそう感とか、
同じスキルであれば、人間やっぱり「なんとなく良さそうな人」に頼みたいですよね。
ただ、難しいのがその後です。
第一印象がすごい良い!!この人と一緒にやりたい!!と思ったとして、
仕事内容や対応が伴わないと目も当てられません。
口頭では調子が良いけど、メールのやりとりになるとうまくコミュニケーションが取れなかったり、
対応が求めているものではなかったり・・・。
意外とこういう人、世の中には多いんじゃないかと思うんです。
私事ですが、今、結婚式準備に大忙しです。
もちろん式場のプランナーさんについてもらってますが、
こちらでも上記のようなことが発生しています。
会ったり、電話したりするとすごく親身に話を聞いてくれて、とても良い人なんです。
ただ、メールの連絡になるとなんとも噛み合わない・・・。
(もしかしたら、お互いに思っているかもしれませんよね。気を付けよう。)
仕事でも、電話や対面よりもメールでのやりとりが主流になっている昨今。
メール上のコミュニケーション(言葉の伝え方、書類の作り方、整え方等)一つで、
相手の印象は全然変わります。
「終わり良ければ総て良し」ということわざはありますが、
仕事でその認識ではアウトですよね。
最初から最後まで印象変わらずに終わらせられる。これがきっとプロのあるべき姿ですね。
自分がサービスを受けることで学べることはたくさんあります。
しっかり自分の業務に落とし込んでいきたいと思います。
「興味」の力
こんにちは!
新宿本社の江川です。
4月に新卒として入社しました。
実は私、いろんな業界に興味があって、就活では業界を絞れませんでした。
いろいろな業界、行政ともつながりがあって、人々の夢を応援できる。
行政書士の仕事は色々な仕事に興味がある私にぴったりだと直感で感じました。
サポート行政書士法人を選んだ理由は色々ありますが、入社してよかったです。毎日学びがあって楽しいです。
さて、入社から一ヶ月、私は許認可の申請書の作成を担当していました。
私は経営学部出身なので、もちろん許認可の申請書なんて見たことがありません。
最初の申請書はなんと6時間もかかりました💦
しかし、だんだんと1許認可1時間で作成できるようになっていき、
今では連携している先輩方にも「書類作成早くなったね」とほめていただけています。
超負けず嫌いの私からすると悔しすぎますが、
初めてのことができないのは当たり前だし、時間がかかるのも仕方ないことです。
ただ、1回でどこまで自分のモノにできるかという点においては、改善の余地があると思っています。
私は「興味を持つ」ことを意識しています。
これは連携している先輩にも言われたことなのですが、興味を持って書類の作成をすることで、
1度に記憶できる量が増えるように思います。
お客様の「会社」にも、「許認可」にも、「事業」にも、もちろん「お客様自身」にも。
「興味」の力は無限大だと感じます。
何事にも興味を持って、楽しく仕事ができたらいいなと思います。
乃木希典の少年時代
20世紀初頭の日露戦争において多大な功績を残した乃木希典は、
陸軍大将としてのイメージからは想像がつかないのですが、
幼少時代は体が弱く、そのうえ臆病な性格だったそうです。
しかし、両親の教育もあり、この弱点を克服することができました。
父は、長府の藩士で、江戸にいましたが、自分のこどもがこう弱虫では困る、どうにかして、子供のからだを丈夫にし、気を強くしなければならないと思いました。
精撰「尋常小學修身書」(小学館文庫) p70より抜粋
(中略)
ある年の冬、大将が、思わず「寒い。」と言いました。父は、「よし。寒いなら、暖かくなるようにしてやる。」といって、井戸ばたへつれて行き、着物をぬがして、頭から、つめたい水をあびせかけました。大将は、これからのち一生の間、「寒い。」とも「暑い。」ともいわなかったということであります。
母もまた、えらい人でありました。大将が、何かたべ物のうちに、きらいな物があるとみれば三度三度の食事に、かならずそのきらいな物ばかり出して、すきになれるまで、うちじゅうの者が、それをたべるようにしました。それで、まったく、たべ物にすききらいがないようになりました。
寒さや苦手な食べ物があったときに、それに徹底的に順応することで克服したのです。
今の時代で同じようなことをさせるのは、体罰のような感じもして些か抵抗がありますが、
時代や環境に特有の要素を除いて上記の話を読むと、考えさせられる部分もありました。
現代は「得意を伸ばす」「好きなことだけで生きていく」といった考えが
広く認められるようになり、だいぶ生きやすい世の中になりました。
一方で、自分にとって都合の良いもの、快適で無害なことに慣れきってしまうと、
少しの環境の変化や困難に対応するだけのレジリエンスも簡単に失われてしまいます。
そして、何より人生の幅が知らず知らずのうちに狭まっていく気がしてなりません。
苦難に遭遇しても努力と忍耐で前へ進んでいくような経験をした人にしか得られない収穫が確かにあると思います。
変化に富んだこれからの時代には、良い変化も悪い変化もあるでしょう。
個人や企業がそうした変化に振り回されず、その時々の目標や理想に向かって進み続けるためには、
コンフォートゾーンを抜け出す勇気と行動も時には役に立つことがあるのではないでしょうか。
仕事は総力戦
こんにちは。名古屋支店の大原です。
今月から新しいメンバーが増え、オフィス内の雰囲気が活き活きしています。
さて、新年度に伴い、社内外で「人事異動」というワードをよく耳にします。
新しい業務にアサインされたり、求められる役割が変わったりと、
それぞれが新しい挑戦をしていく時期かと思います。
ただ、激変の時代の中で、自分の力を試したいからと、時間をかけてじっくりやっていても
100%完璧なものはすぐに出来上がりません。
周りを巻き込んで、いかに早く、確実にゴールに持っていけるかが必要になります。
分からないことは「詳しい人(専門家)」に聞けばいいです。
社内なら詳しい先輩に聞けばいいですし、
社外なら最終目標までの最短ルートを導いてくれる専門家に相談すればいいのです。
それぞれの挑戦、総力戦で挑みましょう。
常識を疑え!
中一の始めの頃、当時所属していたサッカークラブの合宿があり、合宿所で一夜を明かし、朝起きて、使った布団やシーツをたたみ、きれいにしたら監督に激怒されました。
なんで激怒したか分かります?
「お前らは掃除のおばちゃんのことを考えていない」とのこと。
要はシーツをたたんだ状態で洗濯機にかけず、一回くしゃくしゃにする必要があり、たたむと返って手間になるとのこと。
たたむと運びやすいというメリットはあるが、そのメリットとくしゃくしゃにするデメリットを比較すると、シーツはたたまずに一か所にまとめて置くのがベスト、ということでした。
確かに、そんなに大きな合宿所ではなく、洗濯場所も近いのでそれがベストな選択なのかもしれない。
今までたたむことになんの疑いの余地もなく、よかれと思ってやっていたが、そうじゃないことがあるのか、と思い知ったときでした。
サポート行政書士法人のキーワードである、「他者への想像力」とか、「全体最適」とか、「作業的に仕事をやらない」とかの要素が入っているように思います。
一般的によかれと思われていること、大勢がよくやっていることこそ、本当にそれがベストな選択なのか疑う必要があります。
ただ、掃除の人はおばちゃんではなく、お姉さんだったことは口が裂けても監督に言えなかったです。
楽なほうを選んでも良い
人生において、大事な選択肢に直面している時、楽なほうを選んではいけないという言い方には賛成ですが、仕事をする時、楽なやり方を考えない人には注意をしてほしいと思います。
確かに、真面目でコツコツと働く人は多いですが、頑張りすぎている場合もあります。ただ、根性で目の前の難しいことを乗り越えようとするのではなく、楽なやり方を考えることも必要です。それには、周りの人と協力することも大切です。
仕事で楽なやり方を探すことで、自分の時間を大切にすることもできます。毎日へとへとになってしまっては、成長することができません。楽なやり方があるときには、それを活用することで、より効率的に仕事ができるようになるでしょう。
楽なほうを選んでも良い、ということは、自分にとって最適なやり方を見つけることが重要だということです。自分に合ったやり方を見つけることで、より良い成果を出すことができるはずです。
今年度も一緒に頑張りましょう!
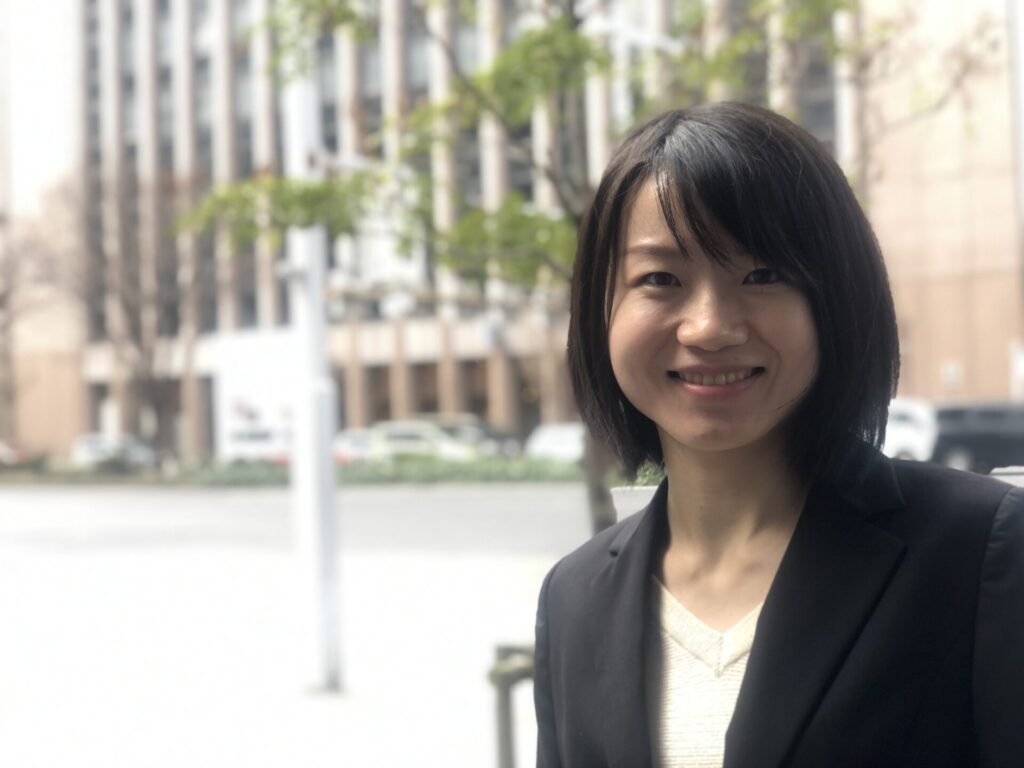
キラキラする
こんにちは。
名古屋支店の榎土です。
少し前まで人数全国2位の名字だったため、
社内では下の名前の「ゆめ」と呼ばれています。
漢字こそ”夢”ではないですが、
名前の由来通り、
夢見がちの少女がそのまま歳をとって
今の私となりました。
キラキラなものが大好きで爪もキラキラさせていますし、
学生時代にはキラキラしたホルンを吹いていました。(ソロパートなども担当していました♩)
中でもキラキラした人が大好きです。
社会人を始めた4月からも
週末はキラキラした人を求めて
歌舞伎、お笑い、ミュージカルと
広く深く色々なものを観に行っています。
また、週末だけでなく
サポート行政書士法人には周りの人のために一生懸命考え、動く方々が
沢山キラキラ輝きながら働いています。
キラキラの過剰摂取です^_^
私もキラキラ輝けるように精一杯頑張ります。

