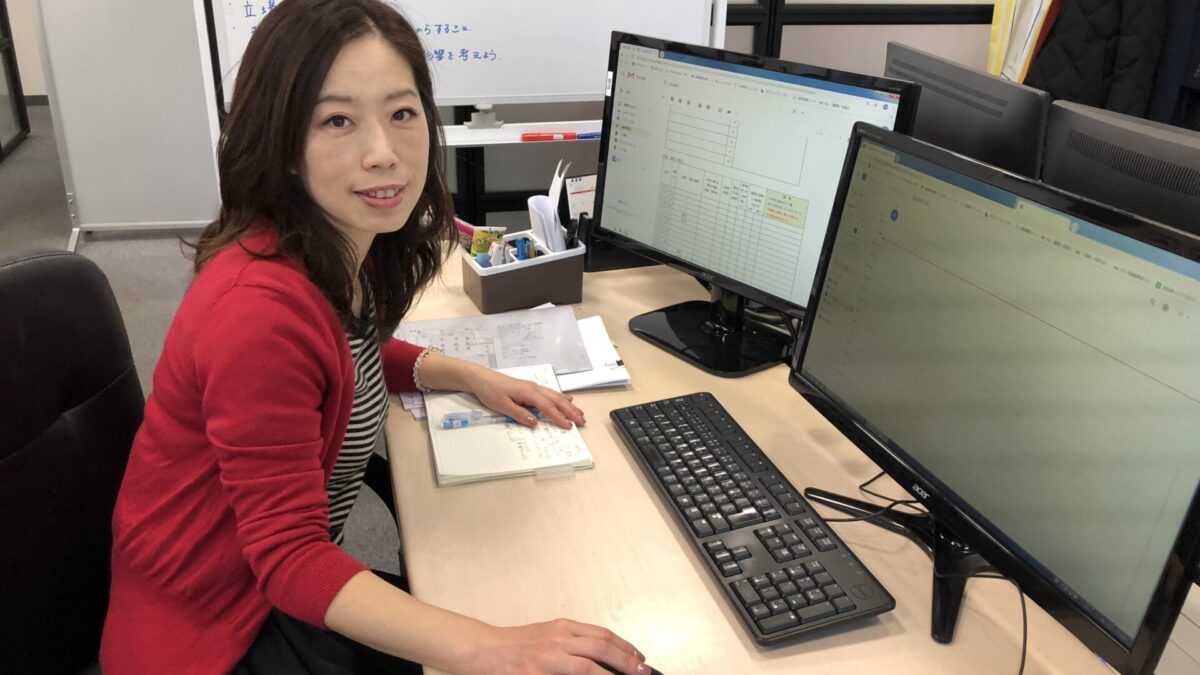こんにちは。
新宿本社の坂本です。
突然ですが、皆さん、最近本読んでますか?
今は動画や漫画等を手軽に楽しめるサブスクが増えていて、本を読む機会って減った気がします。
数年前は、電車の中でも本を読んでいる人、結構いたと思うのですが、
最近はほとんど見ませんね。みんなスマホを見ています笑
もちろん、スマホで本を読んでいる人もいると思うのですが、
私はどうにも紙が好きな古いタイプです。
スマホで読むと文字が滑るというか、うまく頭に入ってこないんですよね。
アナログな古い人間です。。。
ちなみに、本と言っても小説が好きです。学生時代、現代文の授業は苦手なタイプでした笑
最近、「本って能動的だよね」って話をしたんです。
どういうことかというと、
本は自分で文字を追い、頭の中で世界を膨らませて、手でページをめくる。
自ら動くことをしないと進まないものなんですね。
対して、ドラマ、映画、アニメなどの動画は受動的です。
自分が進めたいかどうかは関係なく進んでいきます。
ボーっとしてても入ってくるし、最悪、寝てても進みます。
最近のSNSも受動的ツールの一つだと思います。
アプリを開いたら、いろんな情報が勝手に入ってくる。
スクロールするだけでいろんな情報を手に入れられます。
最近の若者との違いってそういうところにも出てくるのかな、と考えました。
私は図書館世代です。
欲しい本があったら、図書館に行って借りたり、調べものは図鑑や辞典、図書館などで調べました。
能動的に情報を取ることに親しみがあります。
対して、スマホの普及が当たり前になった世代だと、
全て手の中で完結するし、色んな情報が自動的に入ってくることに慣れています。
もしかしたら、図書館世代は情報は取りに行くものと考え、
スマホ世代は情報は向こうからやってくるもの、と考えているかもしれません。
そんな小さな違いが日々の仕事や生活の価値観の違いに発展するのかもしれません。
なんで分からないんだ、ではなく、その人の時代背景に目を向けて、
変化に合わせた関係づくり、組織作りができると良いですよね。
私は、図書館世代と言ってもスマホ大好きです。
でも、たまに情報の洪水に疲れてしまって、無性に本が読みたくなる時があります。
そんな時は、本屋に行って気になる文庫本をいくつか見繕って、
家でTVもつけず落ち着く音楽をかけ、紅茶やココアを片手に本を読む時間を作ります。
本ってヒーリング効果あるんですかね。ものすごく癒されます。
みなさんもデジタルに疲れたとき、そんな時間を作ってみてください。お勧めです。