『スターウォーズ エピソード5』という映画に、
主人公ルークが達人ヨーダからフォースという超能力の特訓を受けるシーンがあります。
沼地に半分埋まった戦闘機をフォースで引き上げろと指示するヨーダに対し、
ルークは「やってみるよ(I’ll give it a try)」と言うんですが、
ヨーダは「やってみるじゃない。やるかやらないかじゃ。
試しはいらない(No. Try not. Do. Or do not. There is no try)」と喝を入れます。
「There is no try」が凄く印象的じゃないですか。
「『試す』や『何となく』で誤魔化すな。覚悟してやれ」ということだと思うんです。
また、中国の歴史書『史記』では、「断じて行えば鬼神も之を避く」との言葉が残されてます。
仕事でもこの感覚は大切です。社内でもこの感覚を持っておらず、
仕事が溜まっていく人が多いかもしれません。
一方、この感覚を持っていると実行力が違うので、仕事が終わっていくようになります。
自分自身、入社当初から原則定時退社ですが、やると決めたことはやるようにしています。
やると決めたら、やる。
只、それだけの気がします。
投稿者: shigyo_user
人を喜ばせることが仕事の本質
怒られないように仕事をする人がいます。
子供時代、怒られながら勉強してきた人は、親や先生に怒られないように行動する癖がついていて、
自分の行動の動機が「怒られないこと」になっています。
ずっと強度のストレスが掛かっているので、長くはもちません。
社会人生活では、遅かれ早かれ、体調不良になってしまいます。
一方、人を喜ばせるために仕事をする人もいます。
うまくいったら、喜ばれて、自分自身の満足感を得られるし、
うまく行かなくても、喜ばせられなかっただけなんで、マイナスにはなりません。
社会人として、長く活躍するには、
仕事を「人を喜ばせられる機会」だと認識することが重要だと思います。
物流2024年問題
3月も中旬になり、暖かくなってきたと思ったら、雪が降ったりと寒暖差が激しい日々が続いていますね。
季節の変わり目の体調管理には注意していきたいです。
さて、2024年の4月からトラック業界は、働き方改革関連法施行による時間外労働の上限規制が適用されます。
1日の拘束時間が現行制度では、最大16時間だったものが15時間へ、休憩時間も継続8時間以上から継続11時間を基本として、下限を9時間に設定。等 労働時間が制限されていきます。
トラックドライバーの労働時間が制限されることにより、起こる問題は以下があげられます。
①1日に運べる荷物の減少
②トラック事業者の売上減少
③ドライバー個人の収入の減少
④③伴って、ドライバー不足
その結果、2030年には輸送能力が30%以上不足すると言われています。
2024年問題を解決するためには、トラック事業者だけが改善をするのではなく、
荷主企業及び消費者個人も協力して解決していく必要があります。
荷主企業は、荷待ち時間や付帯業務などのドライバーの負担を減らすことの協力。
ITツール等のシステムの導入等があげられます。
(実際にドライバーの1日の勤務時間の3分の1ほどが運転以外で発生している付帯業務になります)
消費者個人としては、再配達とならないように、日時を指定し、指定した時間帯に滞在していること。
置き配や受取先の指定(コンビニや指定ロッカー等)をして不在時でも配達完了とできるようにしていくことが大切です。
人から応援されるにはどうしたらいいか
「人から応援されるにはどうしたらいいか」ということを垣間見た出来事がありました。
先日、朝の通勤ラッシュで満員電車に揺られながら座っているときのことです。
車内は緊張に包まれてていましたが、ある駅でドアが開くと、仲の良さそうな四人家族が入ってきました。
若いお母さんが2歳くらいの男の子を抱きしめ、その隣には小学生と思しき、年の離れた姉妹がいます。
姉妹は弟のほっぺたに愛情を込めて触れると、周りの空気が和らぎました。
お母さんは、子どもたちには優しい笑顔を向けています。
私はその家族の姿を見て以来、「席を譲ろうかな」という思いが頭によぎりつつも、
なんとなく様子を見てしまっていたのですが、
お母さんが(少し疲れたのか)キャリーケースの上に男の子を座らせた時、
立ち上がって「この席に座ってください」と声をかけました。
お母さんは笑顔を見せながらも、「このほうが(男の子が)大人しくしているので」と優しく断ります。
それから間もなく、別の乗客がお母さんに席を譲ろうと声をかけました。
そしてまた、同じことがもう一度起こりました。
短い時間で三回も「座ってください」と声をかけられるのを見たことはありません。
人は、明るく頑張っている人を助けたくなる。その人間の心の働きを見たような気がします。
それは、日常だけでなく仕事でも同じです。どうせ頑張るなら、明るく頑張っていきたいと思います。
春
名古屋支店の押谷です。
年度末が近づいてきましたね。
4月からは入学式、新社会人と環境がガラッと変わる方も多いかと思いますが、
それぞれ良いスタートを切ってもらいたいです。
色々な事に挑戦して、たくさん失敗から学んでください。
さらに、今年も、猛暑予想で、厳しい暑さになりそうです。
暑さに慣れる体調管理も早めにしておく必要があるかもしれませんね。

ツールの善悪 ― 効果的な活用のあり方
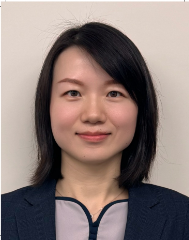
冬の定番として、私は週末によくスノーボードに行きます。数年間やっているのですが、なかなか上達しませんでした。
しかし、先週末に行ったら、急に上手くなりました(笑)。
それは家族の高品質なスノーボードを借りて、ボードにワックスも掛けたからです。普段使い慣れていないものだったので、最初の滑りは戸惑いましたが、滑っているうちにスースー滑り、なんとなくボードと一体化した気がしました。
ボードを変えることでまったく異なる体験ができました。
ツールを上手に活用することが、こんなにも違うことを実感しました。
人間はツールを生み出し、それによって効率的に作業します。
しかし、ツールに過度に頼りすぎると、本来持っている能力が退化する可能性もあります。 例えば、スマホの利用は暇つぶしのために始まり、次第に動画を見るための手段になり、最終的にはスマートフォンから離れられなくなるというような状態です。チャットやSNSは安全な手段ですが、それが原因でリアルな対面会話の機会が減り、リアルタイムでのコミュニケーションが苦手になることもあります。
スマートフォンやバーチャル世界に飲み込まれないように、五感を使った実体験を優先し、日々を過ごしてください。

何事も考えよう、プラス思考で生きる
皆さんは、何にイラっとしますか?
日常生活をしていると、小さいことだけどイラっとすること、気になることとかはないでしょうか?
「店員さんの言葉遣いや接客が気になる」
「この料理の味付けはもうちょっとこうしたほうがいい」
「イベントや展示会等の動線がおかしい」等など、、
私はイラっとした自分を見つけると「なんて心の狭い人だ」と自責をしてしまいがちです。
でも、小さいことが気になるとき、何かに意見が出るときって、その人自身が持っている才能があり、
問題視するポイントが見えるタイミングだとも思うんです。
なので最近は、生活していく上で何に引っ掛かりを感じた時、その先の自分を見つめては、
自分なりの改善策とかを考えてみるようにしています。
皆さんも、感性を働かせて生きてみてください。
意外と見えていない自分が見えるかもしれません。
何事も考えようだと思うので、プラス思考でいきましょう。
自炊生活
名古屋支店の周です。
去年はUber Eatsにドハマり、1ヶ月15回ぐらい注文もする時期があって、
さすがに財布が泣きそうで、今年の1月から毎日自炊することに決意しました。
毎週日曜日に一週間分の食材を買って、浪費したくないので毎日作らないといけなくなります。
そうしないと、すぐに諦めっちゃいそうです…
基本、毎日の料理が決まってます。
月曜日:味付けがしっかりしたスタミナ丼と味噌汁です。にらと豚バラのピリ辛味付けで、ご飯をいっぱい食べて、「今週も頑張るぞ」と思い込み…
火曜日:しめじ・エリンギ・卵・ピーマンの炒め料理。太りやすくなってきたなぁと気がして、少しともダイエットという意味があります。
水曜日:油少なめ焼き餃子。キャベツと挽肉を混ぜて、餃子を包みながらぼーっとします。
木曜日と金曜日:青椒牛肉絲、中華スープ。木曜日からはちょっと作りたくない気持ちが出たので、一気に二日分の量を作っちゃいます。
週末:できれば外食です!
約3か月続けて、Uber Eatsの時期よりは、家計がかなり楽です。そして、体は健康になったと信じています!
たまに新しいレシピを挑戦することも楽しいですよ。
自炊、オススメです!
行政書士試験合格経験談
こんにちは、名古屋の朴です。
令和5年度の行政書士試験に合格しましたので、
独学から始めて試験に合格した経験を共有していと思います。
大きく以下の3つの部分に分けました。
- 時間管理
毎日勉強することは難しいと考えます。
体が疲れる日もあり、ただ勉強する気がしない日もあります。
そこで、私はできるだけ短い時間内に、できるだけ多くの量を勉強しました。
教科書は内容が多いため、毎日続けて勉強すると退屈になります。
そこで、すべての教科書の内容を1週間の間に一度読んでみました。
内容を覚えることが目的ではなく、ただ内容について印象を残すことが目的でした。
一度読んだ後、その次の週に再度教科書を読みました。
2回目からは、メモをとりながら重要だと思われる部分を重点的に理解します。 - 分析能力
教科書を2回程度読んだ後からは、過去問題をみました。
これまでどのような内容が試験に出たのかを分析してみました。
そしてその部分についてさらに詳しく理解します。 - 重点を攻める
すべての内容を完璧に理解して準備して、試験場に入ることはほぼ不可能だと考えます。
そのため得点の割合が最も大きい部分を重点的に攻めます。
得点の割合が最も大きい行政法と民法、この2つの法は絶対に攻める必要がある部分です。
逆にどれだけ時間を費やしても大きな意味がない商法などの場合は、
大胆に捨てても良いと考えます。
以上の勉強方法は、あくまで私自身の勉強方法でした。
結論としては、自分に最も合った効率的な方法を見つけることだと思います。
そして一度でも二度でも、いつかは絶対に
自分で考えてみる
こんにちは!名古屋支店の金井です。
弊社では、社会課題の解決を最優先に、
全社員が3つの経営理念のもと、日々業務に励んでいます。
※詳細はこちら!
中でも、「不満を言わず、対策で解決する」は、
ビジネスにおいても、日常生活においても非常に大切な考え方だと思います。
・学校の先生の教え方が下手だったから、テストの点数が悪かった
・体調が良くなかったので、うまくプレゼンできなかった
・電車が人身事故で遅延したので、会社に遅刻した
・この仕事が上手くいかなかったのは、チームメンバーがミスしたから
・頑固で要求の多いお客さんだったので、クレーム案件になった
これらは、全て「自分以外の何かのせい」にしています。
サポート行政書士法人はそうではなく、「自分で対応すべき未解決の問題」と捉えます
不都合は他責にするのではなく、
自ら考え、対策して、根本的に解決する。
自責思考にすることで、自分を取り囲む人、環境が、
どんどん良いものへと変わっていくはずです。

