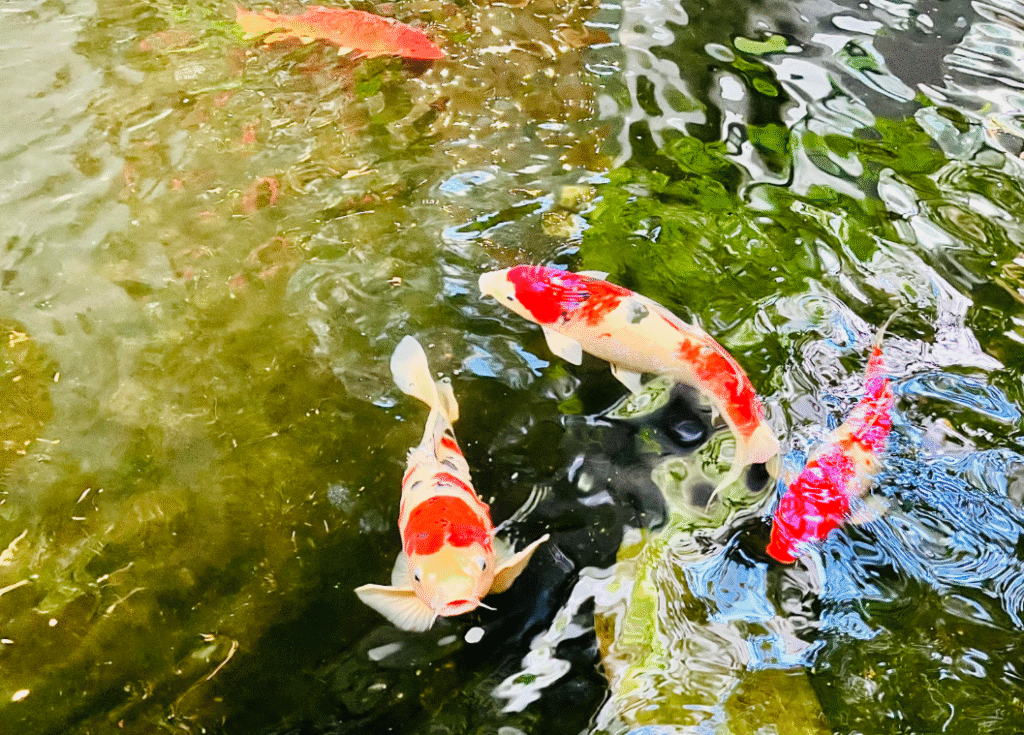名古屋支店の達知です。
今月から、サポート行政書士法人にも新たなメンバーが加わりました。
何名か支店を超えて連携していますが、
皆さん、仕事へのワクワクと社会人になるドキドキが常に伝わってきて、
フレッシュさを感じます。
さて、仕事を始めて、まず躓くのは、失敗したときのリカバリーです。
毎日仕事をすれば、良いことも悪いことも起こり得ます。
大なり小なりあるとは思いますが、恐らく同じくらいの割合で発生している気がします。
学生時代は、授業態度が悪かったり 友人の前で不機嫌でいても
周りが何かあったの?そっとしておこうかな…と気を遣うこともありますが、
社会人になると、そういった場面はほとんどなくなります。
特に、私たちはコンサルタントとしてお客さんと接しています。
いつでも前向きに物事を考え、解決策を見出す必要があるため、
特に、自分の機嫌取り(物事が生じてもすぐに前向きに切り替えできる力)が大事だと感じています。
この切り替え方法は、原因の分析が重要です。
自分の機嫌を客観的に把握して、自分で機嫌を取る。
ぜひ、自分なりのリフレッシュ方法を見つけてほしいです。
ちなみに、私の最近の自分のご機嫌取りは「観葉植物」です。
植物は日光が必須なので、土日も朝一番にカーテンを開けて
たまに時間があるときは、ベランダに出して 一緒に日光浴しています。
写真は、最近お迎えした 観葉植物たちです。
人も太陽の光を浴びると元気になるそうですよ。