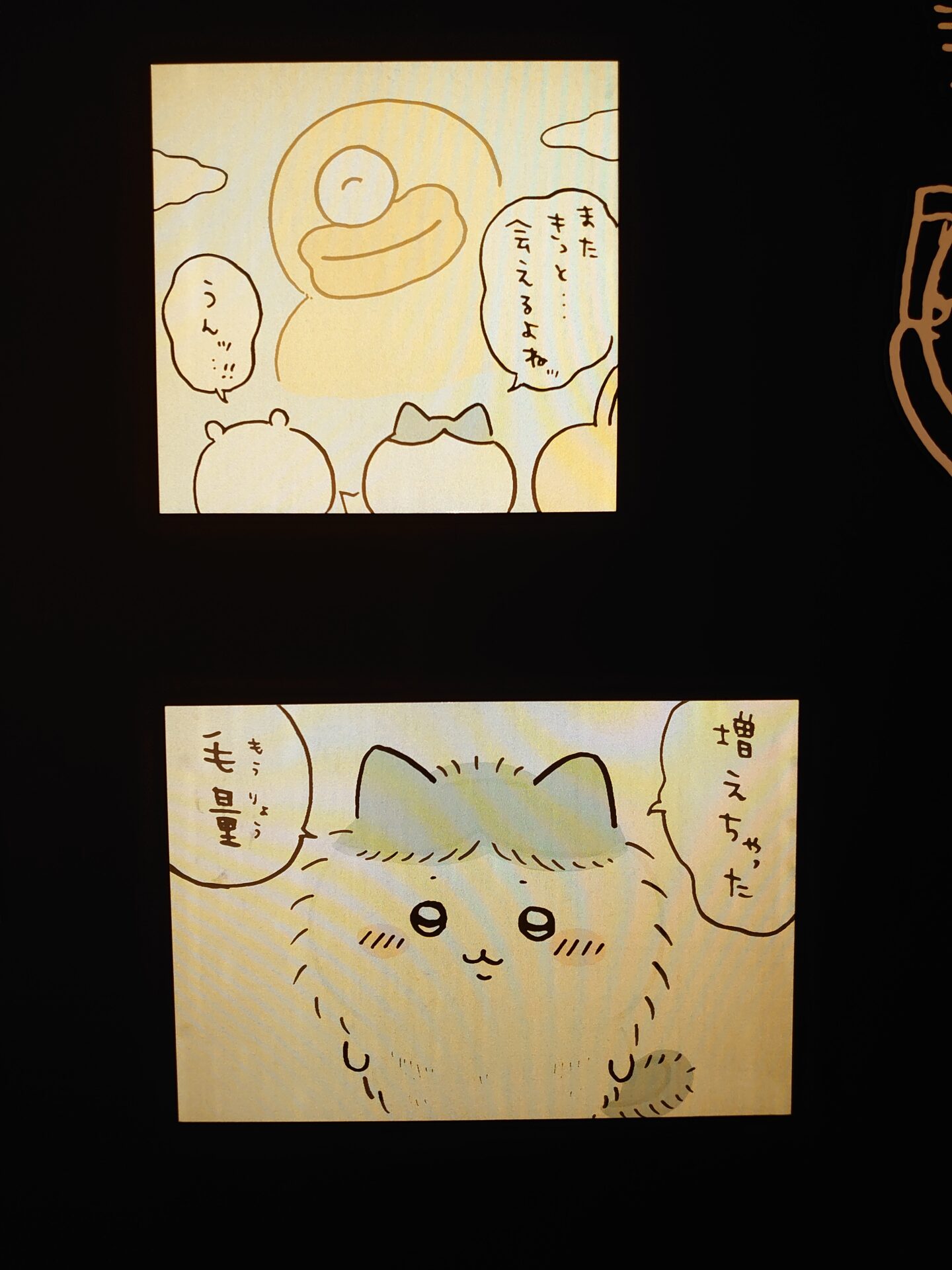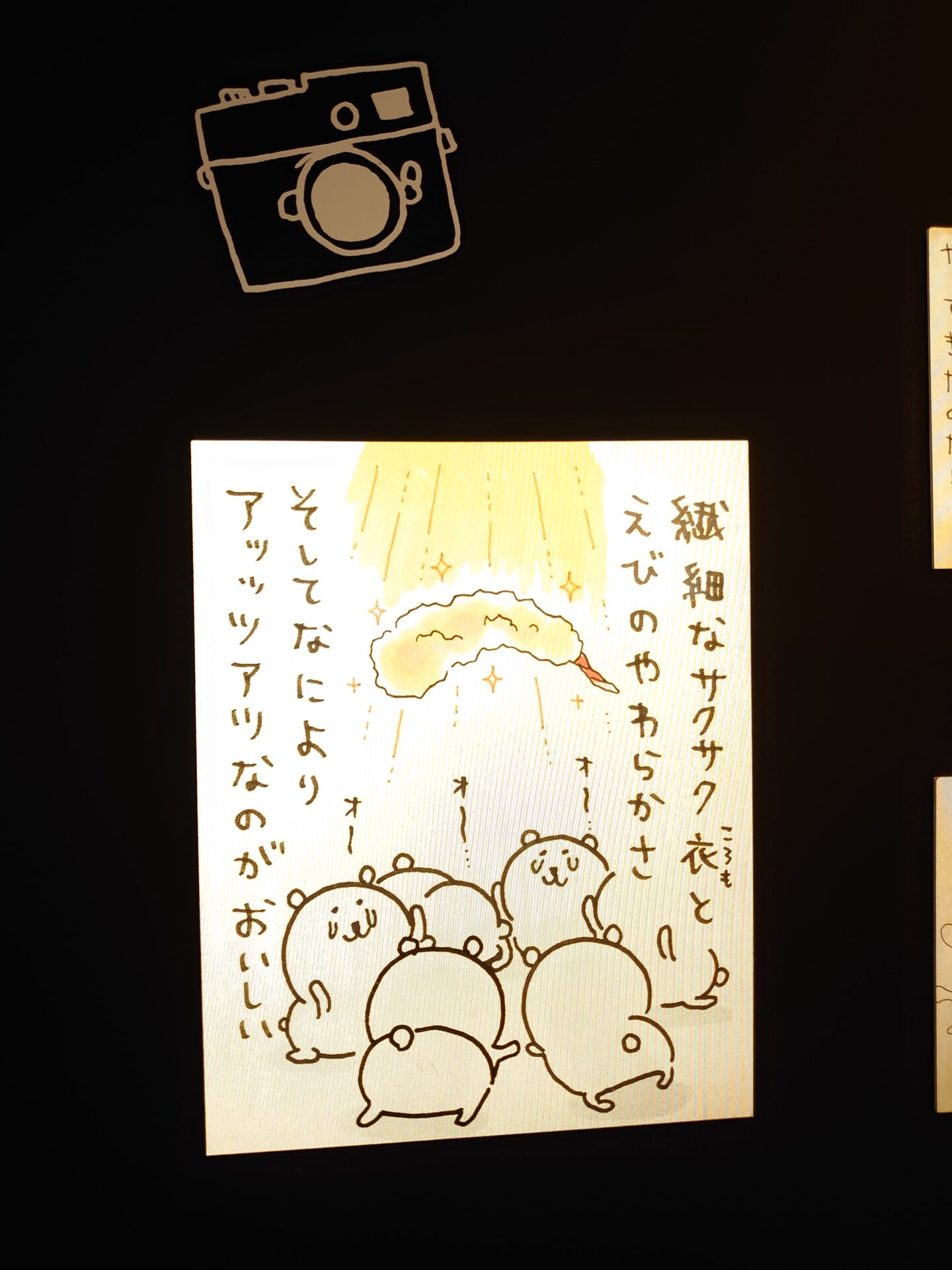こんにちは。
秋葉原支店の山田です。
今月愛媛への出張がありました。
愛媛は毎年のように出張で来させてもらっているのですが、松山の中心地に甲子園常連校の済美高校があります。
この済美高校は、松山のメイン道路にあり、出張の際には必ず学校の前を通ります。
学校の前を通ると済美高校の校訓「やればできる」が校舎の壁に大きく掲げられています。
この済美高校の校訓は、芸人のOBであるティモンディがテレビでよく言っていて有名になりました。
愛媛に来て、済美高校の前を通るたびに、シンプルだけどいい言葉だなと思わされています。
「やればできる」という言葉には次の意味があるようです。
①ポジティブな姿勢
「やればできる」という言葉は、何事も挑戦する意志と自信を持ち、自分の能力や可能性を信じることができます。
②努力と行動
「やればできる」という言葉は、単なる願望や望みだけでなく、実際に努力して行動することが重要であることがわかります。
③挑戦と克服
「やればできる」という言葉は、困難や障害に立ち向かい、それらを克服することができる可能性を表しています。
④成長と実現
「やればできる」という言葉は、自己成長や自己実現に向けての意欲を示します。
在学中に「やればできる」という経験を小さなことでもいいし、ひとつでもふたつでも経験できるなら、社会に出てからも自信をもって生きていくことができるだろうなと思います。
最近オフィス内でチームの仲間と話している中で、「人はかけられた言葉を覚えている」と感じるときが何度かありました。
かけたこちら側からしたらそれほど深い意味はなく発している言葉や何気ない会話のなかでかけた言葉を意外とみんな覚えているのです。
仲間の可能性を伸ばせる言葉をかけていきたいと思います。