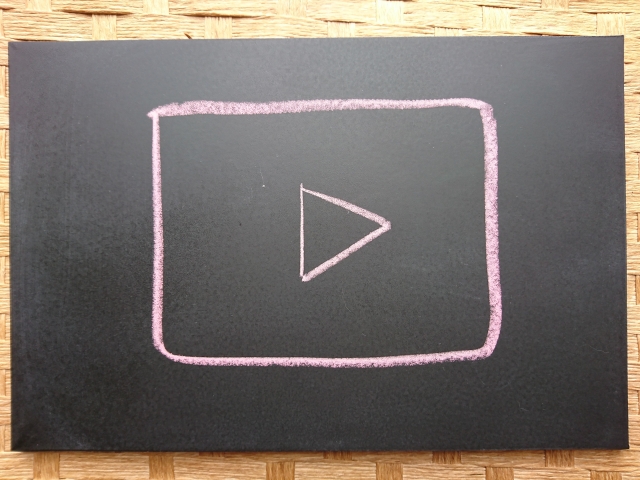こんにちは、増野です。
新入社員の入社時期が近づき、社内でも急増してきた「育成・指導・教育」。
「育成・指導・教育」と聞くと、上司が部下に、先輩が後輩にというように、 上から下に何かを教える場面をイメージしがちです。
でも、実際は、それだけではありません。 「新人や部下が、先輩や上司を育てる」側面が、実は意外と大きな効果を持っています。
これ ↓ は、私のこれまでの経験から確信していることです。 「優秀な新人(後輩・若手)がいるオフィスは、上司・先輩がどんどん成長する」
「優秀な」というのは、仕事ができるということではなく、 「上司・先輩を育てる(上司・先輩のスイッチを押す)」という点で優秀ということ。
特に、SG(サポート行政書士法人)のように平均年齢が低い会社は、 上司・先輩が20代の若手メンバーということがよくあります。
急に上司・先輩になったその人も、まだまだ成長途上で、できないことも山程あります。 でも、これからは自分だけでなく部下・後輩のことも考え、実践して、 今まで以上に成長していかないといけない段階にあります。
優秀な新人(後輩・若手)がいるオフィスは、この段階にいる先輩が、急成長しやすいです。 先輩の顔つき・声色・頼もしさなんかが、どんどん変わっていくので、周りも気づきます。
先輩が一つ階段をあがると、新人の成長余白も拡がり、成長スピードも加速し、 結果として、オフィス全体が成長し、盛り上がっていきます。 それも、とにかく「楽しい!」と感じられる雰囲気で。
では、優秀な新人(後輩・若手)って、どんな人でしょうか。
色々な要素があげられますが、 一番は、「上司・先輩が手応えを感じられる相手であること」だと思います。
どんな相手に手応えを感じるかというと、例えばこんな相手ではないでしょうか。
○上司・先輩とよくコミュニケーションをとっている
○上司・先輩との会話やポイントは、記録(メモ)し、その後も参考にしている
○上司・先輩のどんな小さなアドバイスも、即実践し続けている
○上司・先輩との共有事項については、自ら、その結果や続報を報告・共有している
○上司・先輩から得た学びを、自分以外の周りにも伝承し、活用している
○自分の感想・感情・考え・価値観を、上司・先輩にも伝えている
○明るく前向きに物事に取り組み、自分事として捉えようとしている
○上司・先輩にとってのブレーキ要素が少ない
(過度なプライドの高さ、素直でない、感情や機嫌で動く、体調含め状況が読めない 等)
結局は、「上司・先輩が、自分の存在価値を感じられた時」なんだと思います。
身近な誰かとの関係に手応えが感じられ、自分の行動に価値・意味を感じられると、 少し先の自分やオフィスの状況にも明るい手応えを感じられて、 次のチャレンジや変革の一手を起こしやすくなるものです。
これ、対象を「新人・部下・後輩」に変えてみても、全く同じことが言えると思います。 上記に列挙したような上司・先輩の行動が実感できると、 きっと、新人・部下もやる気スイッチが押されるはずです。
要は、上司も部下も、先輩も後輩も、ベテランも若手も、 相手にとって手応えを感じさせられる自分でい続けることが重要だということです。
さて、それでは、皆さん考えてみて下さい。
自分と関係の深い上司や先輩(部下や後輩)は、この半年・1年の間で何か変わりましたか? 雰囲気、印象、考え方、やり方、行動、人間関係・・・何でもいいです。 次のステップに進んでいる感じがしますか?
もし進んでいる感じがするのであれば、 それは、部下・後輩(上司・先輩)であるあなたの良い影響が出ているんだと思います。
進んでいる感じがしないのであれば、あなたとその上司・先輩(部下・後輩)の関係性は、 変え時かもしれません。
どこかから降ってくる成長チャンスを待つよりも、 ベテランも新人も誰もが、自分の行動で、自分や周りの成長機会を作っていける、 そんな自家発電な会社にしていきたいです(^^)/