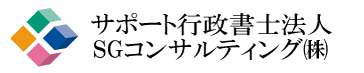化粧品とは?定義や医薬品・医薬部外品との違い
化粧品は、言うまでも無く日常生活で広く使われている製品の一つです。
では、法律では「化粧品」はどのように定義されているのでしょうか。
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(医薬品及び医薬部外品を除く。)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

「体を清潔にしたり、見た目を美しくする目的で、体に塗布等する」ものとは、つまり、化粧水・乳液、保湿クリーム・ファンデーション・口紅・石けん・マニキュアなど、身近な物の多くがこの「化粧品」に該当します。
薬事法の定義の通り、「化粧品」は、あくまでも「人体に対する作用が緩和なもの」に限られます。
この定義に従って化粧品を取り扱う際は、商品中に配合される<成分>及びうたって良い<効果・効能>といった側面から、医薬品医療機器等法(薬機法)上の厳しい制限がかけられています。
ただし、「医薬品」や「医薬部外品」として定義されるものはこの範疇には含まれません。
医薬品・医薬部外品との違い
医薬品医療機器等法(薬機法)では、「医薬品」や「医薬部外品」については、「化粧品」とは別に定義しています。
|
■治療等が目的となる「医薬品」 例)薬局等で販売されている風邪薬等の内服液、軟膏、目薬 etc ■予防(殺菌・除菌等)等が目的となる「医薬部外品」 例)薬用化粧品、美白クリーム、歯周病予防歯ミガキ粉 etc |

それぞれ使用目的が異なる「化粧品・医薬部外品・医薬品」ですが、人体に与える影響の強さは化粧品<医薬部外品<医薬品の順に大きくなっていきます。
化粧品・医薬部外品・医薬品のどれに該当するのかによって、商品中に配合して良い成分とその分量やうたって良い効果・効能等が変わってきます。
海外の化粧品の取り扱いを検討される場合は、その国ごとに薬事上の規制が異なる為、特に注意が必要です。
例えば海外では化粧品に入れても良い成分が、日本では配合NGの成分であったり、海外では認められる効果・効能の表示が、日本では表示が認められないといったケースが、多く見られます。
化粧品の効能範囲
化粧品の効能の範囲については、以下のように規定されています。
- 頭皮、毛髪を清浄にする。
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 毛髪にはり、こしを与える。
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 毛髪をしなやかにする。
- クシどおりをよくする。
- 毛髪のつやを保つ。
- 毛髪につやを与える。
- フケ、カユミがとれる。
- フケ、カユミを抑える。
- 毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 髪型を整え、保持する。
- 毛髪の帯電を防止する。
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- (洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- 肌を整える。
- 肌のキメを整える。
- 皮膚をすこやかに保つ。
- 肌荒れを防ぐ。
- 肌をひきしめる。
- 皮膚にうるおいを与える。
- 皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 皮膚の柔軟性を保つ。
- 皮膚を保護する。
- 皮膚の乾燥を防ぐ。
- 肌を柔らげる。
- 肌にはりを与える。
- 肌にツヤを与える。
- 肌を滑らかにする。
- ひげを剃りやすくする。
- ひげそり後の肌を整える。
- あせもを防ぐ(打粉)。
- 日やけを防ぐ。
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- 芳香を与える。
- 爪を保護する。
- 爪をすこやかに保つ。
- 爪にうるおいを与える。
- 口唇の荒れを防ぐ。
- 口唇のキメを整える。
- 口唇にうるおいを与える。
- 口唇をすこやかにする。
- 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 口唇を滑らかにする。
- ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 口中を浄化する(歯みがき類)。
- 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1) 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2) 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3) ( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7518&dataType=1&pageNo=
化粧品の成分基準
化粧品には、配合成分に関する厳しい基準があります。
主要なポイントは以下の通りです。
①ネガティブリスト
化粧品に配合してはならない成分、または配合が制限されている成分のリストです。
防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素などが含まれます。
②ポジティブリスト
特定の条件下でのみ配合が許可されている成分のリストです。
③医薬品成分の配合禁止
化粧品には、添加剤としてのみ使用される成分を除き、医薬品の成分を配合してはなりません。
ただし、医薬品の成分であっても、平成13年3月31日までに既に承認を受けた化粧品の成分である場合、または化粧品種別許可基準に掲げられていた成分については、承認された成分の分量または許可基準に掲げられた分量に限り配合が認められている場合があります。

化粧品の製造と安全性の確保
「消費者への必要な情報提供を確保した上で、消費者の需要の多様化に対応したより多くの選択を可能にする」という方針のもと、化粧品基準が定められています。
化粧品基準は、消費者が自分に合った製品を選びやすくするためのものであり、その中には化粧品の成分に関する規定や製造過程における安全管理の手順が含まれます。
化粧品に配合される成分については、以下のような対応が求められます。
①安全性の確認
化粧品製造販売業者は、配合成分の安全性を十分に確認し、その適否を判断する責任があります。
このため、業者は科学的なデータや臨床試験結果を基に成分の安全性を評価し、その結果に基づいて使用の可否を決定する必要があります。
安全性の確認は製品の品質を保証するために欠かせないステップです。
②資料の収集と保管
配合成分および製品の安全性に関する資料を収集、作成し、保管する必要があります。
これには、成分の起源や製造方法、使用履歴に関する情報が含まれます。
また、収集した資料は製品の安全性を証明するために必要なものであり、製造販売業者はこれらの資料を適切に管理し、必要に応じて提出できる状態にしておくことが求められます。
資料の適切な管理により、製品のトレーサビリティを確保し、万が一の問題発生時に迅速に対応しやすくなります。
化粧品に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で化粧品業界へ参入される方から、既存の製造販売業者・製造業者・販売業者の皆さまに対して、医薬品医療機器等法に関する手続きサポートやコンサルティングを行っています。
化粧品の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つです。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。