外国人の日本国籍取得手続き
~帰化申請の流れと必要書類・条件を詳しく解説~
更新日:2025年7月4日
◆もくじ◆
帰化と永住の主な違い

帰化とは?
帰化とは、外国籍だった人が日本国籍を取得することを指し、毎年多くの外国人が帰化申請を行っています。
手続きは法務局で行われ、最終的な許可を出すのは法務大臣です。
日本に帰化するには、日本に一定期間以上住み続ける必要があります。
一般的には、継続して5年以上日本に住所を有し、生活基盤を築いていることが求められます。
また、申請者は安定した収入があり、自立した生活を営んでいる必要があります。
さらに、当然ながら日本語能力も重要な要件の一つであり、日常会話に支障がないレベルであることが求められます。
永住(永住権)とは?
永住権は、外国籍のまま日本に永住する権利を指します。
永住権を持つことで在留期間の制限がなくなり、更新手続きや活動内容の制約もなくなります。
ただし、国籍は元のままであり、選挙権など、帰化したら付与される一部の権利は付与されません。
永住権の申請には、一般的には、就労や学業などの正当な理由で、継続して10年以上日本に在留している必要があります。
また、安定した収入と社会的な信用があることも求められます。
永住権を取得すると、他のビザ(在留資格)で設けられていた就労制限がなくなり、職業選択の自由が広がります。
さらに、日本での生活が安定し、将来的な不安が軽減されます。
帰化と永住の具体的な違い
弊社への問い合わせの中で、「永住か帰化、どちらの方向に進むべきか?」という問い合わせを多くいただいています。
日本で長く安定的に暮らしていきたいとお考えになる方も増えているように感じます。
では、具体的に永住と帰化でどのような違いがあるのでしょうか?
➀日本在留に関する手続き
帰化すると、日本国籍を取得するための手続きが必要ですが、一度取得すれば、その後は在留に関する手続きが不要になります。
一方、永住権の場合は、最初の申請後も更新や各種手続きが必要です。
永住権を持つことで、就労や居住に関する制限が大幅に緩和されますが、定期的な在留カードの更新が必要です。
②国籍
帰化の場合は日本国籍を取得できますが、永住権では国籍は変わりません。
帰化によって日本国籍を取得すると、母国の国籍を放棄する必要がある場合があります(二重国籍の解消)。
この手続きを経て、日本国民としての権利と義務を享受することができます。

③戸籍
帰化した人は自分の戸籍を持つことができますが、永住権を保有しているだけでは戸籍を持つことができません。
戸籍があると、日本国内での身分証明が容易になり、多くの場合、永住権を保有しているだけの場合よりも行政手続きもスムーズに行うことができます。
④参政権の有無
帰化すると日本の選挙権を持つことができますが、永住権では選挙権はありません。
帰化することで、日本の政治に直接参加する権利が得られ、政治的な意思表示ができるようになります。
⑤退去強制処分の扱い
例え永住権を持つ場合でも、一定の犯罪行為を犯すと退去強制処分の対象となることがあります。
一方、一度帰化すると日本国民としての権利を持つことになるため、退去強制処分は下されなくなります。
帰化によって、日本国民としての法的保護を受けることができ、生活の安定が図られます。
⑥母国への入国
永住者の手続きは、永住ビザ取得前と変わりません。
一方、帰化した場合は、日本人としての入国手続きが必要となります。
⑦海外旅行について
海外旅行の手続きは、渡航先と国籍国によってかわってきます。
永住者の場合には、永住ビザ取得前と手続きは大きく変わりません。
帰化した場合には、日本人として150以上の国に、ビザを取得せず旅行できます。
【帰化と永住:条件の違い】
| 永住 | 帰化 | |
| ①意味 | 外国の国籍のまま、日本に継続的に居住が可能 | 日本の国籍を取得し、日本人として居住が可能 |
| ②ビザ更新 | ビザの更新→不要 在留カードの更新→必要(7年に一度) | 不要 |
| ③就労制限 | 制限なし ※公務員については国籍条項により、永住ビザでも就労できない職種があります。 | 制限なし |
| ④名前 | 外国名のまま | 自由に決めることが出来ます。※日本の名前に使える漢字、ひらがな、カタカナ以外は使用出来ません。 |
| ⑤パスポート | 外国パスポートのまま | 日本のパスポートの発行が可能 |
| ⑥戸籍 | 自分の戸籍は持てない | 自分の戸籍を持てる |
| ⑦参政権 | 選挙権・被選挙権がない | 日本国籍となるため、選挙権・被選挙権がある |
日本への帰化のメリットとデメリット
帰化のメリット
➀日本のパスポート取得
帰化すると、日本のパスポートを取得できます。
日本のパスポートは国際的に信頼されており、ビザなしで訪問できる国が多いため、海外旅行がしやすくなります。
その数は世界でも一二を争う水準です。

②日本名の取得
帰化すると日本人としての氏名を持つことができ、日本社会で生活がしやすくなります。
日本名を持つことで、日常生活やビジネスの場面でのコミュニケーションが円滑になり、日本社会にもスムーズに溶け込みやすくなります。
③戸籍の作成
帰化することで日本の戸籍を持つことができます。
家族全員が同じ戸籍に入ることができる場合もあります。
戸籍の作成は、婚姻や出生などの家族関係を公式に証明するための重要な手続きです。
帰化のデメリット
また、日本は二重国籍を認めていないため、帰化によって母国での権利(財産権や相続権など)を失うリスクがあることが主なデメリットと言えます。
また、帰化を申請する際の手続きが煩雑で時間がかかることもデメリットと言えるでしょう。
帰化申請の要件
帰化申請には一定の要件があります。
例えば、日本に一定期間以上住んでいることや、安定した収入があることなどが求められます。
また、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」のそれぞれに異なる条件が設定されています。
普通帰化では、継続して5年以上日本に住所を有することが必要です。
簡易帰化では、親が日本人である場合や、日本で生まれた場合などに要件が緩和されます。
大帰化は、特別な功績がある場合に適用される特例です(※過去に適用された事例はありません)。

帰化するための詳しい要件は、以下のとおりです。
「自分の場合、どうなんだろう?」
「よくわからない・・・」
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
帰化するための基本要件
| 条件 | 補足説明 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①引き続き5年以上 日本に住所があること | 継続して5年以上滞在していることが必要。中断があれば最初から再計算。正当な在留資格も必要。 | |||||||||||
| ②18歳以上で行為能力があること | 成年に達しており、法律的な能力があることが必要。 | |||||||||||
| ③素行が善良であること | ー | |||||||||||
| ④生計を営むに足る 資産または技能を有すること | 世帯単位で判断。申請者本人に収入がなくても、配偶者や親族の収入等で可。 | |||||||||||
| ⑤国籍を有していない、 または日本国籍取得により 他国籍を喪失すること | 原則として多重国籍は認められない。 | |||||||||||
| ⑥暴力団関係者でないこと | ー | |||||||||||
| ⑦日本語の読み書き能力 | 小学校3年生程度の日本語の読み書きができることが望ましいとされている。 |
居住条件(条件①)について
帰化申請のポイントの1つに居住条件があります。
帰化の条件となる5年の居住条件を満たしていても、
下記に該当するような場合は申請が難しくなります。
1) 居住の継続性
連続して約3ヵ月間の間、日本を離れていると、
それまでの居住歴はなくなり、ゼロからカウントをし直すことになります。
また、連続していなくても日本を離れている日数が多いと、
それまでの居住歴がなくなり、カウントをし直すことになる可能性があります。
2) 留学から就労に変わった場合
留学生としての経験のみ、5年以上であっても帰化申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、
居住条件は満たしたことにはなりません。
※ただし、10年以上日本に在留している場合は、居住10年として申請することが可能です。
素行条件(条件③)について
帰化申請の条件の一つとして、「素行が善良であること」があります。
具体的には、下記に該当していなければ素行が善良であるといえます。
1)法律違反
大きな犯罪行なうことは当然ですが、
交通違反などについても帰化申請には影響があります。
短期間での反則金レベルの交通違反や、
略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、
数年間時間を置いてから帰化申請を行なうほうがよいです。
2)脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行なっている方の確定申告です。
適切に納税をしてきていないのであれば、
きちんと納税を行なってから申請を行なう必要があります。
特例措置(条件の免除)
通常の場合は条件の1~6の条件を要しますが、
日本人と結婚された方や養子関係にある外国人については、条件が一部緩和されることがあります。
以下の条件に当てはまれば、特例措置として当てはまる条件が免除されます。
■条件①(居住用件)が免除される場合の条件
・過去に日本国民であった方の子で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有している。
又は
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父か母が日本で生まれた。
又は
・引き続き10年以上日本に居所を有している。
——-
■条件①②(居住要件、年齢要件)が免除される場合の条件
・日本人の配偶者である外国人の方で、
引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有している。
又は
・日本人の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、
かつ引き続き1年以上日本に住所を有している。
——-
■条件①②④(居住要件、年齢要件、収入要件)が免除される場合の条件
・日本人の子で日本に住所を有している。
又は
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組時点では未成年だった。
又は
・かつて有していた日本の国籍を失っており、現在日本に住所を有している。
又は
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方で
その時から引き続き3年以上日本に住所を有している。
【帰化と永住:申請要件の違い】
| 永住 | 帰化 | |
| ①申請・提出先 | 各地域管轄の出入国在留管理局 (一般的に入管と呼ばれる) | 各地域管轄の法務局 |
| ②審査期間 | 約6ヶ月~1年程度 ※コロナの影響もあり審査期間が長引いている傾向です。 | 約8ヶ月~1年半程度 ※コロナの影響もあり審査期間が長引いている傾向です。 |
| ③居住要件 | 一般的には継続して10年以上 日本に居住していること ※一部緩和要件あり | 一般的には継続して5年以上 日本に居住していること ※一部緩和要件あり |
| ④日本語能力 | 日本語能力は申請要件ではありません。 | 日本語の読み書き・話す能力が必要です。 一般的には小学校3年生以上のレベルは最低限必要 |
| ⑤収入要件 | 直近5年の毎年の年収が300万円を超える必要あり。 ※一人・扶養なしの場合 | 明確に収入金額だけで判断する基準はありません。ただ一般的に見て日本で安定的に生活できるレベルの収入や貯金、仕事の状況かを確認されます。 |
| ⑥審査結果 | ・許可の場合 許可の通知書が届きます。その後入管にて在留資格が永住者となっている在留カードを受領します。 ・不許可の場合 入管にて不許可理由を確認することができます。それを元に問題点を解消後、再申請が可能です。 | ・許可の場合 官報に帰化の許可がおりた方の氏名と住所が公表され、法務局の担当官から連絡が来ます。 ・不許可の場合 不許可理由を教えてもらえませんので、自身で推測し問題点を解消後、再申請が可能 |
帰化申請が完了するまでに必要な日数
帰化申請が完了するまでの期間は、多くの申請者様にとって重要な関心事です。
この期間は一概に断言できず、申請者の個別事情や申請先の法務局の混雑状況、申請内容の複雑さによって大きく変動します。
一般的に、帰化申請の準備から最終的な許可通知までは、全体で約1年から1年半程度を要します。
この期間には、膨大な必要書類の収集と作成に費やす時間も含まれます。
法務局に申請書が受理されてから許可が官報に告示されるまでは、概ね1年程度が目安ですが、経歴が複雑な場合や必要書類に不備がある場合は、審査期間が2年以上に及ぶこともあります。
また、申請先の法務局によっても審査の進捗や案件数が異なるため、地域によって審査期間に差が生じることもあります。
申請者様には、この審査期間が長期にわたる可能性を理解し、着実に準備を進める姿勢が求められます。
帰化申請が遅れる要因とは
帰化申請の審査期間が長引く主な要因は多岐にわたります。
最も多いのは、提出された必要書類の不備や不足です。
書類に漏れや誤りがあると、法務局から補正指示が出され、その対応に時間がかかると全体の審査期間が延びます。
次に、申請者様の個別事情が審査を複雑にするケースです。
例えば、転職回数が多い、過去に犯罪歴や交通違反歴がある、税金や年金の滞納がある、生計状況が不安定、海外滞在期間が長い、家族が海外にいるといった事情は、より慎重な審査を要するため、審査期間が長引く傾向にあります。
これらの場合、詳細な説明や追加資料の提出が求められ、準備に時間を要します。
さらに、法務局側の内部事情も審査期間に影響を与えます。
特定の時期に申請が集中したり、担当官の人員配置や異動があったりすると、審査が滞る可能性があります。
近年は特に、法務局側での審査が長引く傾向にあります。
また、面接のスケジュール調整がスムーズに進まないことや、申請者様が法務局からの連絡に迅速に対応できないことも、審査停滞の原因となります。
帰化申請の受付から承認までの期間
帰化申請は、必要書類の提出だけで完結するものではなく、受付から最終的な承認(許可)までに複数の段階を経る複雑なプロセスです。
この一連の流れ全体が帰化申請の期間を構成します。
まず、法務局での事前相談を経て、膨大な必要書類の収集と作成に入ります。
この書類作成だけで通常1〜2ヶ月を要します。
全ての書類が揃い、法務局に申請書が正式に受理されると、本格的な審査期間が開始されます。
申請受理後、法務局の担当官による厳密な書類審査が始まります。
書類の内容が正確か、不足がないかなどがチェックされ、必要に応じて電話照会や追加書類の提出が求められます。
書類審査が進むと、申請受理から通常2〜3ヶ月後に申請者様ご本人との面接が実施されます。
面接では、帰化申請の動機や日本での生活状況、家族関係、生計状況などが詳細に質問され、申請者様の意思や適格性が確認されます。
面接後も、法務局は申請者様の身辺調査や関係機関への照会を継続します。
税金や年金の納付状況、公的記録の確認、必要に応じた職場や近隣住民への聞き取り調査などが行われます。
面接から最終的な許可・不許可の通知までは、概ね10ヶ月程度を要すると言われています。
これらの調査が完了し、法務局内で最終判断が下されると、法務大臣に上申され、許可・不許可が決定されます。
許可された場合は官報に告示され、申請者様に許可通知が送付され、一連のプロセスが完了します。
期間短縮のためにできること
帰化申請の審査期間を少しでも短縮し、スムーズな許可を目指すためには、申請者様自身が積極的に準備を進めることが非常に重要です。
最も効果的なのは、帰化申請前の段階で徹底的な事前相談を行うことです。
法務局の担当官や、帰化申請に精通した専門家(行政書士など)に相談し、ご自身の個別事情でどのような必要書類が必要か、注意点などを確認することで、書類の不備による補正指示を最小限に抑えることができます。
次に、必要書類の収集と作成は、可能な限り正確かつ迅速に行うべきです。
戸籍謄本や住民票、納税証明書など、公的機関から取得する書類は発行に時間がかかる場合があるため、早めに手配を始めることが肝要です。
ご自身で作成する書類(履歴書、動機書、生計の概要など)は、事実に基づき、漏れなく、かつ法務局の担当官が分かりやすいように具体的に記載することが求められます。
曖昧な表現や矛盾した内容があると、法務局からの質問が増え、審査期間が延びる原因となります。
この点において、専門家である行政書士のサポートを受けることで、書類作成の質を高め、審査期間の短縮に繋がる可能性が高まります。
帰化申請の流れ
帰化申請は、申請書類の作成→申請受理→審査(面接・調査)→許可というプロセスで進みます。
ここでは、弊社でサポートする場合の帰化申請手続きの流れをご説明します。
① 初回面談
⑴ ヒアリング
初回面談で必要な書類を確定。
必要な書類は、国籍・家族構成・お仕事など具体的な条件によって変わってきます。
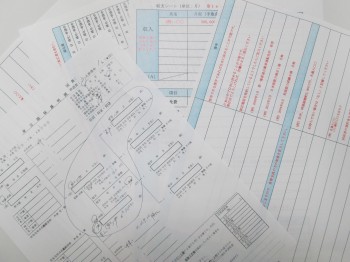
「どんなお仕事?」「離婚歴はありますか?」「ご両親は健在?」「収入はどれくらい?」など立ち入ったことまで、初回の面談にて詳しくお話をうかがいます。
⑵ 必要書類の確定
ヒアリングをもとに、まずは最低限どんな書類が必要かを確定し、ご説明します。
(書類の内容によっては法務局から指示が出ることもあります。)
本国、日本の書類、税金関係、運転の記録、出入国関係・・・
必要な書類の量と幅広い種類に、驚かれる方も多いです。

⑶ 委任状の作成(捺印)
代理取得可能のものは弊社で書類取得を行います。
お休みをとってわざわざ役所に出向く必要はありません。
会社経営者の方になると、委任状だけで10枚以上になることも!

② いよいよ書類取得・作成手続きのスタート
⑴ 各種証明書を取得
各証明書類には有効期限があります。
また、請求してから取得するまでに日数を要するものもあります。
(ちなみに、法務省に請求する「閉鎖外国人登録原票」「出入国記録」は取得に1ヶ月以上時間がかかります。)
取り直しの手間は避けつつ、効率よく書類を集めるスケジュールを組んでいきます。
※代理取得ができないものに関しては、取得手続きをお願いしています。
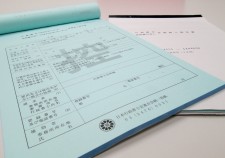
⑵ 申請書類の作成
決められた様式で申請書を作成していきます。

ご家族構成、職歴、引越し歴、1ヶ月の家計、借入れ、預貯金などなど。
一緒に提出する書類との間に矛盾がないか、しっかりチェックしながら作成していきます。
③ 法務局での書類点検
地域によっては、申請受理前に法務局で申請書類のチェックを行います(「書類点検」と言われています。)
ここで、書類の確認、ヒアリングを受けつつ、申請者の状況に応じてさらなる書類を指示されます。
具体的な書類名ではなく「こういうことが証明できる書類を持ってきて」といわれることも・・・
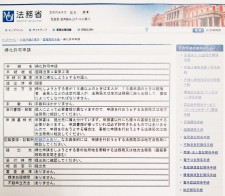
申請前に、審査をしてくれる法務局での確認をしてもらえるのはありがたい反面、「受付可能」のお墨付きをもらえないと申請は受理されません。
④ 申請受理
いよいよ申請。申請受付は申請者本人が行います。
「受付ってどんな感じなの?」「法務局の担当者って厳しいんでしょ?」「申請の日は普段着でいいの??」
皆さん、不安に思われることは一緒。安心して手続きできるようアドバイスします!
⑤ 審査開始
申請受付から2~4ヶ月後に面接があります。
面接で聞かれることも、実に様々。
管轄法務局にもよりますし、国籍、個人の状況によって全く違います。
数時間かかったというかたから、「10分で終わりました!」というかたまで。
その方の状況に応じてアドバイスを行います。
⑥ 許可
官報に公示されるほか、法務局の担当者から直接本人に連絡が入ります。
おめでとうございます!
手続きのイメージをつかんでいただけたでしょうか?
帰化申請をスムーズに進めるポイントは、
「いかに適切な書類を効率よく集めるか?」です。
サポート行政書士法人では、そのかたの事情に最適なコンサルティングを行い、
一日もはやい日本国籍取得をサポートします。
帰化が決まった後に必要な手続き
帰化者の身分証明書の受取り
帰化が許可されると官報に氏名と住所が掲載されます。法務局から帰化が許可された旨の連絡があり、
法務局で今後の手続きに関する説明があります。
帰化届の提出
帰化が認められたら住所地の市区町村へ「帰化届」を提出する必要があります。
これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
このとき添付書類として「帰化者の身分証明書」も一緒に提出します。
「帰化届」の書き方については法務局で説明を受ける際に用紙と記入例を記載したものが配布されます。
配偶者が日本人の場合
配偶者が日本国籍の場合は、その日本人配偶者の戸籍謄本を添付が必要となるケースがあるため、事前に市区町村に確認をしておいたほうがよいでしょう。
配偶者の本籍地が現在の住所地であるならば問題ありません。
国籍離脱の手続き
帰化許可前までに、国籍離脱の手続きを行っている場合(台湾人、ベトナム人など)と、
国籍離脱の手続きを行わないまま、帰化許可を取得する場合(韓国人など)があります。
帰化許可前までに国籍離脱の手続きをしている場合は、特に手続きは必要ありませんが、
手続きを行っていない場合は、帰化後に本国に対して国籍離脱の手続きをする必要があります。
必要書類等は国によって違いますので、大使館・領事館で確認してください。
運転免許証・パスポートの手続き
運転免許証については、変更の手続きが必要となります。
パスポートについては、新たに発行手続きが必要となります。
その他の手続き
法人、不動産の登記名義人、銀行口座の名義人、
営業許可証の氏名、その他帰化が許可される前にしていた契約など、
帰化後に変更手続きが必要なものもありますので、ご注意ください。
帰化申請の注意点
公的支払い審査
帰化申請の際には、税金や年金、その他公共料金の支払い状況が審査されます。
これにより、申請者が日本社会において法的な義務を果たしているかが確認されます。
未払いがある場合や、遅延が続いている場合は、申請が認められないことがあります。
面接
申請後には面接が行われ、申請者の生活状況や日本への適応度が確認されます。
面接では、申請書類に基づいて具体的な質問がされるため、準備が必要です。
面接では、申請者の日本語能力や生活態度、社会的な適応度が評価されます。
帰化事例の紹介
弊社で実際に扱った、いくつかのケースについて、ご紹介します。
CASE1 ~40代中国人男性~
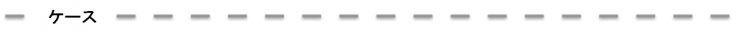
弊社の日本語テスト対策プログラムを活用し、満点が取得できるレベルにまで、サポートしました。
日本語テスト合格までに期間があったため、
その間に申請書類を整えておき、合格後すぐに申請できました。
ただ、書類取得段階で、日本人の前妻から書類取得の協力をしてもらうことができずにいました。
そこで弊社が間に立ち、
前のお客様へ必要な理由を丁寧に説明したことで、書類のご準備にご協力いただけました。
法務局への同行ご希望だったため、19万円でサポートさせていただきました。
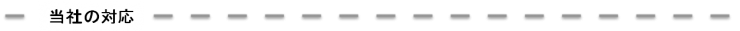
●40代中国人男性
●大学から渡日
●元はご自身で大阪にて帰化申請をする予定で、日本語テストも合格していた
●名古屋に転居し、再度日本語テストを受けたが何度受けても受からず手続きが進まない
●日本人の前妻が、書類などの協力を拒んでいる
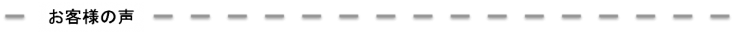
なかなか次のステップを案内してもらえず月日が経ち、
自分も他県への移動があり…と半ばあきらめていましたが、
御社に相談したことで合格できなかった日本語テストも
しっかりサポートしてもらえてクリアし、無事、許可をもらうことができました。
今までずっと帰化できるか不安だったので、今すごく晴れやかな気持ちです。
CASE2 ~20代ブラジル人女性 定住者~
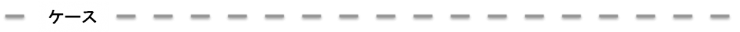

●20代ブラジル人女性 定住者
●日本生まれ日本育ち
●両親が要件を満たさないため未成年時に帰化できず、二十歳なったのを機に申請
●雇用形態が不安定で生計要件に懸念点あり
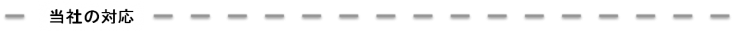
職歴や雇用形態が不安定で行政担当からは許可は難しいのではと判断されていました。
法務局と話し合いを重ね、申請者が継続して働く意志があること、
日本国籍を取得したら仕事の幅を広げて色んなことに挑戦したいという思いを
動機書に記載していただいたことで、申請受付となり、数カ月後、許可となりました。
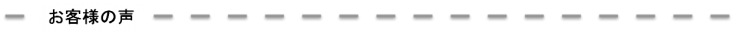
ずっと日本国籍を取得したいと思っていたため、20歳を機に帰化申請しようと決意しました。
要件は満たしていると思っていましたが、
仕事状況から生計不安定と判断がされ、次のステップを案内してもらえませんでした。
御社に相談したところ、法務局の担当員と協議して、ステップを進めてくれただけでなく、
自分の想いを動機書に書き、申請しようとアドバイスをくださいました。
おかげで無事許可となりました。
次の夢は新しくもらった日本のパスポートで、夢だったハワイへ行くことです。
CASE3 ~70代朝鮮籍女性 特別永住者~
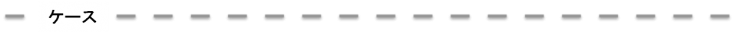
●70代朝鮮籍女性 特別永住者
●日本生まれ日本育ちだが保存期間が過ぎており証明書が取れない
●両親や兄弟が既に亡くなっており協力者がいない
●朝鮮(韓国)の書類が取れない
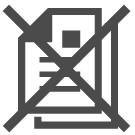
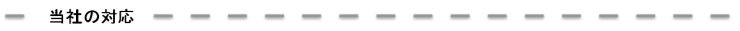
朝鮮籍の方は、その登録がないために韓国領事館で書類を取得ができず、
加えて日本にも登録がない方でしたので、
どこの国にも自分の国籍を証明する書類がなくパスポートを作ることができませんでした。
日本での書類が取得できなかったことの証明として、
各自治体に証明書がないことの証明書を出してもらい、申請を進めました。
晴れて許可になったので、
日本のパスポートでご友人と海外旅行に行くのを楽しみにしておられます。
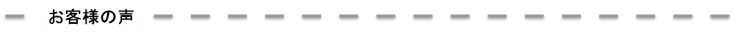
朝鮮に自分の登録がないこと、また自分が日本で生まれた証明などが
取得できないことで、こんなに根拠資料が複雑になるとは思いませんでした。
もし、自分で帰化申請をしていたら、途中で諦めていたと思います。
御社は、代わりの案もすぐに提案してくださり、プロに任せてよかったと思いました。
自分のパスポートもやっと作れたので、友人や家族と海外へ遊びに行こうと思います。
本当にありがとうございました。
CASE4 ~20代韓国人女性 特別永住者~
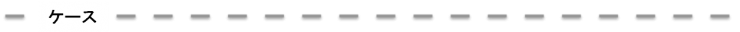
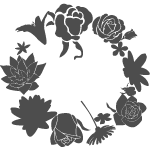
●20代韓国人女性 特別永住者
●日本生まれ日本育ち
●まわりの人には、韓国籍であることを知られていない
●日本人の恋人と結婚する予定で、結婚前に帰化したい
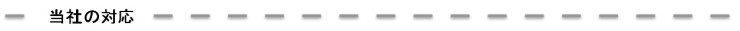
帰化申請の要件はクリアしていましたが、
仕事が忙しくとても自分では申請用意するのは難しいと考えてご相談にいらっしゃいました。
恋人や家族とも、日本国籍を取得してから婚姻届けを提出する方向で話を進めており、
早く申請するように急かされていらっしゃる状態でした。
お申し込みをいただいたのち、
お客様もスピーディーに書類のご準備を進めていただきましたので、許可までとてもスムーズでした。
結果的にお二人の望んでいた日に無事に婚姻届けを提出できたと伺っております。
なお、時期によっては間に合わないこともありますが、
結婚・出産・就職等で帰化申請を急ぐ場合は早めにご相談にお越しいただくことをおすすめします。
【弊社報酬 16万(翻訳料金別)】
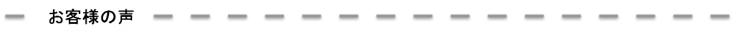
無事に許可がおり、ほっとしました。
須藤さんのおかげで、スムーズに進みました。
ありがとうございました。
CASE5 ~30代韓国人男性 特別永住者~
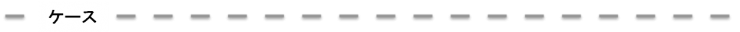
●30代韓国人男性 特別永住者
●会社経営者、個人事業主として生計を立てている
●事業が忙しく、自分で帰化申請の準備が難しい

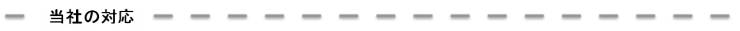
仕事が忙しく、量の多い帰化申請の準備を億劫に感じていらっしゃいました。
また、会社経営者・個人事業主であることで、より多くの書類が必要であったため
弊社で必要な書類をピックアップし、
「後は提出のみ!」というところまで弊社で進める形でサポートさせて頂きました。
韓国書類については取得や翻訳の他にも、家系の時系列についても明確にし、
ご自身の戸籍の動きについて新たな発見があったとのことです。
当日の申請もスムーズに進み、時間の無駄なく申請まで進むことができました。
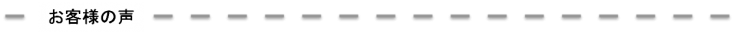
法人や個人事業の書類に関して、
どのようなものを準備すればいいかわからず、戸惑いましたが必要なものをピックアップして頂き、
準備を進められたおかげで無事申請までたどり着けました。
一人ではあの書類の量を準備できなかったのでサポートして頂き大変助かりました。
まとめ
帰化と永住にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
帰化することで日本国籍や選挙権などの権利を得ることができますが、元の国籍を失うリスクや手続きの煩雑さもあります。
永住権は日本での生活の安定をもたらしますが、選挙権などの権利は得られません。
特にスポーツ選手が帰化を選択することが多いのは、日本代表として国際大会に出場するための目的が大きいです。
日本国籍を取得することで、より多くの権利が与えられ、競技活動においても有利な立場を得ることができます。
帰化申請はサポート行政書士法人にご相談ください!
サポート行政書士法人では、帰化や永住権の申請支援を行っています。
初回の相談は無料でお受けしていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弊社に依頼するメリット
➀成功報酬制
面談時や申込後に伺った内容を元に申請を進めて不許可になってしまった場合は、弊社へお支払いいただいた報酬を原則全額ご返金します。
②書類の作成・収集をサポート
必要な書類の案内、証明書類のチェック、申請書の作成までまとめて弊社の専門コンサルタントにお任せください。
③公的証明書を代理で取得
住民票など、日本の公的証明書は弊社で代わりに取得します。
申請されるご本人様が全ての資料を取り寄せる必要はありません。
※基本的に外国書類はご本人での取得になりますが、韓国の証明書については弊社で代理取得可能です。
④外国語の翻訳も対応
英語、中国語、韓国語の翻訳にも対応しています。
※帰化申請にあたっては日本語能力も要件の一つとなります。
書類等の翻訳は対応していますが、弊社コンサルタントとの面談等でのやり取りは
日本語のみの対応となりますので、予めご了承ください。
⑤2500人以上の帰化実績
設立初期から帰化業務に力を入れており、合計1400件以上の帰化案件をサポートしてきました。
※家族での申請案件も多数取り扱っており、合計実績人数は2500人以上!

これまでの帰化申請取り扱い国
韓国、中国、台湾、ベトナム、フィリピン、バングラデシュ、インドネシア、タイ、ペルー、シリア、ミャンマー、アメリカ、ロシア、フランス、ブラジル、ラオス、シンガポール、イラン、キルギス、トルコ、パラグアイ、イラン、ニュージーランド等
関連記事
帰化についてよくあるご質問
帰化申請にはどの程度の日本語能力が求められますか?
だいたい小学校3年生程度読み書きができる日本語能力が求められています。 申請時には「動機書」の自筆で作成します。
帰化申請の手続きはどこで、どうやって始めるの?
日本国籍の帰化申請は、お住まいを管轄する法務局で行います。
申請を始めるには、まず法務局に電話をして予約を取る必要があります。
いきなり行っても受付はしてもらえないので、必ず事前に電話で確認します。
帰化申請にはどんな費用がかかるの?
法務局への帰化申請自体は無料ですが、必要書類(戸籍謄本や住民票など)の発行手数料や、書類の翻訳を依頼する場合の費用がかかることがあります。
また、行政書士など専門家に依頼する場合は別途費用が発生します。
帰化申請の面接でよく聞かれる事は何ですか?
面接では、帰化の動機、申請書に書かれている内容などについて、 聞かれます。
無職でも帰化申請できますか?
帰化申請者自身が無職でも、 同居している家族等に安定した収入があれば申請は可能です。
帰化許可後の名前は自由に決められますか?
ひらがな、カタカナ、人名漢字表に記載された漢字の範囲内であれば、 自由に決めることができます。 ただし、夫婦の場合は、姓は同じにする必要があります。 (法務省サイトで確認できます。)
審査には、どのくらいの期間がかかりますか?
審査は通常8ヶ月~1年程度かかります。 特別永住者の方については審査期間が短縮され、 比較的短期間で許可されることもあります。
一度申請で不許可になった場合、再び申請できますか?
不許可の事情が解消できれば、申請が可能な場合もあります。





