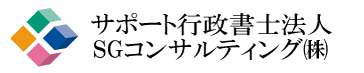【景品表示法】ステルスマーケティングは法令違反!基準と問題点をわかりやすく解説
投稿日:2024年5月27日

ステマは法令違反!景品表示法の観点から法規制の専門家がわかりやすく解説
ステルスマーケティング(ステマ)は、日本のみならず海外でも普及している販売促進手法ですが、消費者庁が定める景品表示法に抵触する可能性があるため問題視されています。
特に日本国内では消費者庁による監視が厳しく、違反が発覚した場合の罰則も厳しいため、ステマに関する法的問題を避けるには、基準を明確に理解し遵守することが求められます。
この記事では、ステルスマーケティングが景品表示法にどのように関連するか、基準や法規制の背景、具体的な対応方法について詳しく解説します。
景品表示法に基づく適正な広告表示とは?
マーケティング活動において、消費者に対する誤解を避けるためには景表法に基づく適正な広告表示が欠かせません。
景品表示法は不当表示を防ぐための法律で、その目的は消費者に対して正確で信頼性のある情報を提供することにあります。
この法律に従うことは、法令遵守だけでなく、企業のブランド信頼性を高めるためにも重要です。
この項目では、景表法の目的や主な規定、そして具体的なステルスマーケティング対策について詳しく解説します。
広告運営に携わる皆様にとって、法規制遵守のための実践的なアドバイスを提供し、消費者と信頼関係を築くための手助けをします。
景表法を適切に理解し、透明性のある広告戦略を構築しましょう。
景品表示法の目的
景品表示法の主な目的は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤認を防ぎ、公正で透明な市場を作ることです。
この法規制は、広告表示において過大な表現や不当な優位性を示す行為を禁止し、消費者が正確な情報を基に合理的な選択を行えるようにすることを目指しています。
具体的には、ステルスマーケティングなどの誤解を招く表示を規制しています。
マーケティング担当者や広告運営に関わる事業者にとって、これらの法律を遵守することは信頼性の向上につながり、消費者が商品やサービスを適切に評価できるようになります。
景品表示法の理解と対応は、消費者にとっても企業にとっても不可欠です。
表示の定義と媒体
「表示」とは、事業者が商品やサービスの品質、規格、価格などを消費者に知らせる手段全般を指します。
具体的には、テレビやラジオの広告、インターネット上のバナー広告、電子メール、店舗でのPOP広告やチラシなど多岐にわたります。
これら全てが景品表示法の規制対象です。
消費者が商品やサービスを合理的に選ぶための基準となる表示には、チラシ、パンフレット、カタログ、新聞、雑誌、テレビCM、ラジオCM、セールストーク、電子メール、アフィリエイト広告、ポータルサイトの口コミ、生活応援SALE、パッケージ、容器ラベル、ディスプレイ(陳列)、実演広告、ポスター、看板、サロンバナー広告、オンラインモール、SNSの投稿などがあります。
マーケティング担当者や広告運営に関わる事業者は、これらの表示が景品表示法に適合しているかを常に確認し、法規制に対応することが重要です。
不当表示の種類と具体例
景品表示法における不当表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、およびその他の誤認表示の3つに分類されます。
消費者庁はこれらの基準を厳格に管理しており、違反すると違法性が問われます。
例えば、優良誤認表示では、実際の品質を過大に宣伝するケースが該当します。
有利誤認表示は、価格や条件について誤った情報を提供する場合で、消費者が実際よりも有利だと誤解する内容です。
その他にも、数量や取引条件について誤導する情報が誤認表示に含まれます。
企業は消費者庁の基準を遵守し、違法性を避ける広告運営が求められます。
⑴優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品の品質や性能について実際よりも著しく良好であると一般消費者に誤認させる表示を指します。
景品表示法第5条第1号に基づき、商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に反して著しく優良であると誤認させる表示は禁止されています。
具体的には、商品に関する成分(原材料、純度、添加物など)や性能、効果、鮮度などの属性に誤りがある表示が該当します。
例えば、ある化粧品がほぼ全てのシミを完全に消すという表示が科学的根拠なしに行われた場合、優良誤認表示となります。
さらに、規格やその他の内容に関しても注意が必要です。
国や公的機関が定めた要件に基づく等級などの表示や受賞の有無などは、商品・サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼします。
例えば、育毛剤があたかも発毛効果があるかのように表示したり、自社の就職支援サービスの成功率を誇張した表示などが含まれます。
⑵有利誤認表示
有利誤認表示は、商品の価格や取引条件が実際より優れていると消費者に誤認させる表示のことを指します。
景品表示法第5条第2号では、商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しています。
例えば、「期間限定で50%オフ」と宣伝しながら、実際には常にその価格で販売している場合は、これに該当します。
価格その他の取引条件は商品そのものを除いた条件を指し、価格、料金、数量、支払条件、景品類、アフターサービスなど広範囲に及びます。
このような誤解を与える表現を避けるためには、正確な情報提供が不可欠です。
例として、通常販売価格よりも高い価格を併記し、実際の販売価格が安く見えるように表示する場合や、脱毛エステの料金を実際よりも低く表示して誤解を招くような場合が含まれます。
⑶その他の誤認表示
景品表示法第5条第3号では、優良誤認表示や有利誤認表示に加え、一般消費者が誤認する可能性のある表示を特に指定して禁止しています。
これには「この薬を飲むだけで確実に痩せます」といった健康被害のリスクを隠す表示も含まれます。
例えば、無果汁の清涼飲料水に果肉の写真を使用し、無果汁であることを明示しない場合も不当表示です。
また、実質年率が明記されていない消費者信用の融資費用の表示、取引できない物件を掲示する不動産広告、原産国を偽る表示なども不当表示に該当します。
ステルスマーケティングとは?
ステルスマーケティングとは、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する手法を指します。
消費者に自然な口コミやレビューと信じ込ませ、購買意欲を高めることを目的としていますが、この手法は景品表示法やその他の広告規制に抵触する可能性が高いです。
例えば、SNSの投稿やレビューサイトの口コミは、一見すると消費者やインフルエンサーの意見のように見えることがあります。
しかし、実際には製造者や販売者が自ら行った広告表示であるケースも存在します。
景品表示法では、広告であることを隠す行為を不当表示として規制しています。
消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べるようにするためには、広告であることが明瞭でなければなりません。
広告であることが分からない場合、消費者はそれを第三者の意見と誤認し、中立的な立場からの推奨だと捉えてしまいます。
したがって、消費者保護の観点からも正確で明確な表示を行うことが重要です。
ステルスマーケティングが疑われる行為は公正取引委員会の監視対象となり、法的措置が取られるリスクを伴います。
マーケティング担当者や広告運営者は、このような法規制をしっかり理解し、遵守することが求められています。
ステルスマーケティングに関する告示の内容
ステルスマーケティングに関する告示は、公正取引委員会によって、消費者保護を目的として発表されています。
この告示では、広告であることを明確にしない宣伝行為が不当表示とされ、その具体的な基準が示されています。
例えば、ブログ記事やSNS投稿において広告であることを明示する必要があり、インフルエンサーによるプロモーションも透明性を確保することが求められます。
また、レビューサイトでの自己宣伝の禁止も重要なポイントです。
さらに、令和5年3月28日内閣府告示第19号では、事業者が行う表示が一般消費者にとって判別困難な場合、不当表示となると明記されています。
具体的には、事業者の供給する商品や役務に関する取引について行う表示が対象であり、その内容が一般消費者に広告と分かるようにする必要があります。
「事業者の表示」とは、供給する商品・サービスの品質、規格、価格などについて一般消費者に知らせる全般的な広告を指し、事業者自身が表示を直接作成しなくても第三者に依頼・指示する場合も含まれます。
規制の対象となる事業者と行為
ステルスマーケティング規制の対象となるのは、商品やサービスを提供するすべての事業者および広告代理業者です。具体的な行為には、以下のようなものが含まれます。
まず、SNSやブログでの偽の口コミ投稿があります。
これは、実際に商品やサービスを利用していない人が肯定的なレビューを投稿する行為です。
また、インフルエンサーに報酬を支払いながら、その投稿が広告である旨を明示しない場合も規制の対象です。
さらに、第三者を装って口コミを投稿したり、レビューサイトで高評価を操作する行為も違反となります。
景品表示法では、インターネット上の表示(SNS投稿、ECサイトのレビュー投稿など)だけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの表示も対象です。
これにより、消費者庁は広範な表示媒体で基準を設け、事業者の透明性と公正性を確保しています。
違反したらどうなるの?
ステルスマーケティングに違反した場合、事業者には重大な罰則が科される可能性があります。
具体的な措置として、公正取引委員会からの警告や改善命令が発せられます。
また、違反行為が認められた際には、企業名の公表が行われ、それによる社会的信用の低下が避けられません。
さらに、経済的な罰金や賠償責任、訴訟のリスクも発生する可能性があります。
消費者庁による調査の結果、違反が認められた場合も措置命令が行われ、その内容は公表されます。
措置命令の具体的な内容としては、違反表示の差止め、違反行為の一般消費者への周知徹底、再発防止策の実施が含まれます。
さらに、優良誤認や有利誤認が認められた場合には、追加の景品表示法上の措置が取られることになります。
事業者の表示と判断される場合
消費者に混乱を招く可能性がある表示が事業者によると判断される具体的な状況を以下に示します。
まず、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合です。
例えば、個人のレビューや口コミが実際には企業の意図的な宣伝である場合や、第三者を装ったプロモーション行為が明らかになった場合が該当します。
また、広告であることを不明示にして商品やサービスの宣伝を行った場合も同様です。
事業者が明示的に依頼、指示をして第三者に表示させた場合や、従業員が事業者の意図に沿った表示を行った場合も事業者の表示とみなされます。
こうしたケースでは、事業者は従業員の役職や担当業務、表示内容の決定にどの程度関与していたかを総合的に判断します。
例えば、商品の販売担当者がSNSに自社商品の画像や文章を投稿する場合や、競合商品を低く評価する投稿を行う場合、これらは事業者の表示とされる可能性があります。
事業者はこれらを避けるために、消費者に誤解を招かない明確な情報提供を行う必要があります。
特に、インフルエンサーや第三者に対する明示的な指示や要求がない場合でも、経済上の利益を提供することにより、その影響を与える状況が示される場合、事業者の表示とされることがあるため、対策が求められます。
規制対応上の注意点(対応すべき基準と措置)
ステルスマーケティングとは、消費者に広告とわからない形で商品やサービスを宣伝する手法です。
このような手法は信頼性を損なう可能性があり、日本では景品表示法の規制対象です。
景品表示法第26条によれば、事業者は不当表示を防止する体制を整備する義務があります。
消費者庁は、これを実現するための「管理上の措置の指針」を定めており、事業者が自らの表示だけでなく、インフルエンサーやアフィリエイターによる表示も管理することが求められます。
管理上の措置には、景品表示法の徹底、法令遵守の明確化、表示内容の確認と情報共有、表示管理担当者の設定、不当表示発生時の迅速な対応が含まれます。
具体的には、社内研修の実施や、インフルエンサーとの契約における法令遵守の明文化、不当表示の発見時には迅速な周知と修正が求められます。
事業者がこれらを適切に行うことで、ステルスマーケティングに対する規制を厳守し、消費者の信頼を維持することが重要です。
行政書士法人による「規制一括管理」サポートのご案内
弊社では、クライアントの規制対応の実施状況や課題等に応じて、主に以下の支援を提供しています。
対象規制等の洗い出し
ヒアリングや実態調査の結果を通じ、現在の事業内容及び今後の事業展開をふまえ、キャッチアップ/留意すべき法規制等を洗い出します。
社内で洗い出した規制一覧に、外部の目線を入れることで抜け・漏れを予防したり、定期的な適用規制の見直しにも、活用いただけます。
対象規制への対応
洗い出した法規制等への適切な対応に向け、必要な支援を、弊社コンサルタントが一定期間伴走する形で実施します。
支援内容例
- 必要な社内体制・業務フローの構築支援
- 効果的な規程・マニュアル等の策定支援
- 各種法令やガイドライン等の法改正アラート配信
- チェックリスト・実務様式の策定支援
- 役職員の教育・研修(コンプライアンス指導等)
- 許認可一括管理・資格者一括管理(有効な資格管理・更新)
- 行政相談・行政相談同行
- 新規事業・法改正時の規制調査・規制リスト作成 等
規制対応状況の監視・モニタリング支援
洗い出した法規制等への対応状況、社内規程等の実行状況等、規制対応に関する不正・問題発生等の確認・監視を目的に、業務の実態調査(内部監査)を実施します。
予備・実地調査後、規制対応に関する不備事項・問題点等を洗い出し、報告書として報告します。(ご希望に応じて、講評会・改善支援も可)