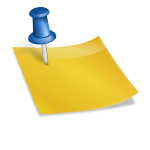決済代行に必要な許認可とは?金融許認可の専門家が解説!
更新日:2025年11月18日
ネットでの買い物やキャッシュレスが当たり前になった今、カード決済や口座振替、ウォレット等を束ねる「決済代行」の役割は急速に重みを増しています。
もっとも、事業の立ち上げ・運用には、資金決済法や割賦販売法、銀行法などの枠組みを前提とした制度理解が欠かせません。
制度設計を誤れば、業規制に抵触しうるだけでなく、業務停止や罰則の対象となるおそれもあります。
本記事では、決済代行に関連する主な許認可について、専門家の視点でわかりやすく整理します。

目次
そもそも決済代行とは
決済代行は、お店やサービス提供者(加盟店)の代わりに、お客様から代金を受け取り、支払い処理をまとめて行う仕組みが一例として挙げられます。
クレジットカード、コンビニ払い、銀行振込、口座振替、電子マネー、携帯料金との合算払い(キャリア決済)など、いろいろな支払い方法を一つの窓口で導入・管理できることが多いです。
お店側は、支払い方法ごとに個別契約やシステム接続をする手間を減らせるうえ、入金の管理や売上の照合、不正利用への対応も一本化できるのが大きな利点です。
なぜ決済代行サービスの提供に許認可が関わるのか
決済代行の事業を新しく始めるときは、多くのケースで国への登録や許可が必要になります。
お客様からお金を預かる性質のサービスであるため、利用者の資金を安全に守ることとサービスの信頼性を確保することがとても重要だからです。
そのため、事業を始める前に、自分たちのサービスがどの法律のルールに当てはまるのかを整理し、求められる登録・許可を正しく進めることが、運営の前提になります。
特に、どのようなサービスを提供し、どのような顧客層をターゲットとし、いかにして収益を上げていくのか等、行いたいビジネスモデルの詳細を明確にしていくことがポイントです。
決済代行のビジネスモデルごとに必要な許認可
以下に、決済代行で採りうる代表的なモデルを「どの許認可に該当するか」についてまとめます。
【クレジットカード番号等取扱契約締結事業】加盟店とカード会社を仲介する場合
クレジットカード番号等取扱契約締結事業とは、販売業者に対して、クレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約(加盟店契約)の締結を行うことを指します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業は割賦販売法上の制度であり、行いたい場合は管轄の経済産業局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことがクレジットカード番号等取扱契約締結事業に該当します。
- アクワイアラー(※1)として、小売店やECサイト等と加盟店契約を結び、加盟店がカード決済等を行えるようにカード会社(イシュアー)との取次を行うこと
- 決済代行業者(※2)として、加盟店との契約締結権についてアクワイアラーから包括的に授権され、小売店やECサイト等と加盟店契約を結ぶこと 等
(※1)英語で「Acquirer」と書き、「獲得する者」という意味で、割賦販売法では、立替払取次業者と定義される。
(※2)ここでいう決済代行業者は、PSP(Payment Service Provider)のこと。クレジットカード決済やQRコード決済等の決済システムを導入したい事業者とアクワイアラーを仲介し、決済システムを提供している業者。
【資金移動業】利用者間の送金サービスを提供する場合
資金移動業とは、銀行以外の者が為替取引(※3)を業として営むことを指します。
資金移動業は資金決済法上の制度であり、行いたい場合は管轄の財務局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことが資金移動業に該当します。
- 顧客から依頼を受けて、海外送金(国内→国外、または国外→国内)を行うこと
- 払い戻し可能な電子マネーサービス(いわゆる●●Pay等)を提供すること
(※3)顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること。
クロスボーダー収納代行サービスへ資金移動業の規制が適用に
これまで規制のグレーゾーンになっていたクロスボーダー収納代行(国境を越えた収納代行)サービスについて、令和7年6月の資金決済法改正(1年以内に施行。経過措置あり。)によって、資金移動業の規制が適用されることになりました。
具体的には、海外のECサイトの決済代行業者が日本国内の顧客から代金を受け取り、それを海外の販売者に送金するようなサービスが該当します。
従来、このようなサービスはその事業スキームによっては資金移動業(送金サービス)に該当せず「収納代行」として扱われるケースがありました。
金融庁は、事業者からの「具体的にどのようなビジネスが規制の適用対象となるのか」「適用除外を定める内閣府令はどのような規定になるのか」などの相談について、直接の相談窓口を開設しています。
【前払式支払手段発行業】ポイントや電子マネーを発行する場合
前払式支払手段発行業とは、商品券・ギフトカード・アプリ内の電子マネーやポイント等、あらかじめ代金を受け取って価値を発行し、その価値で商品やサービスの支払いができる仕組みを発行・管理することを指します。
前払式支払手段発行業は資金決済法上の制度であり、ビジネスモデルに応じて管轄の財務局への申請又は届出が必要です。
具体的には、以下のようなことが前払式支払手段発行業に該当します。
- 自社グループの店舗だけで使える電子マネー・商品券(自家型)
⇒ 未使用残高が基準日(毎年3月末・9月末)に1,000万円を超えた場合、届出が必要 - 複数の加盟店で利用できるプリペイド・ギフトカード・電子マネー(第三者型)
⇒ 発行前に申請が必要(利用開始前に要手続)
【電子決済等代行業】銀行システムと連携する場合
電子決済等代行業とは、銀行とオープンAPIの契約を締結し、銀行口座の送金指図や照会を行うことを指します。
電子決済等代行業は銀行法上の制度であり、行いたい場合は管轄の財務局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことが電子決済等代行業に該当します。
- 複数の振込先への銀行振込の依頼をワンクリックで行うことができるサービス(決済指図伝達サービス)を提供すること
- 預金口座の残高や利用履歴等の情報を銀行から取得・集計し、自動的に家計簿を作成するサービス(口座情報取得サービス)を提供すること 等
【銀行代理業】銀行の委託を受けて金融取引の媒介を行う場合
銀行代理業とは、銀行のために、①預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介、②資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介、③為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行うことを指します。
銀行代理業は銀行法上の制度であり、行いたい場合は管轄の財務局への申請が必要です。
具体的には、以下のようなことが銀行代理業に該当します。
- 店舗窓口やオンラインで、普通預金や定期預金の契約申込~締結までを、特定の銀行の代理として受け付けること
- 法人の資金決済サービス導入時に、当該銀行との取引契約の締結を代理・取次すること(手続案内や申込受付を含む) 等
注:銀行代理業許可については弊社のサービス対象外です。
【図解】それぞれの許認可の違い
| 業態 | 業務範囲 | 法体系 | 監督官庁 |
|---|---|---|---|
| クレジットカード番号等取扱契約締結事業 | 加盟店獲得や立替払取次 | 割賦販売法 | 経済産業局 |
| 資金移動業 | 為替取引 | 資金決済法 | 財務局 |
| 前払式支払手段発行業 | (プリペイド等)発行・管理 | 資金決済法 | 財務局 |
| 電子決済等代行業 | 銀行口座の送金指図や照会 | 銀行法 | 財務局 |
| 銀行代理業 | 銀行業務の代理・媒介 | 銀行法 | 財務局 |
許認可を取得するまでの具体的な手続き
許認可を取得する場合、①事業内容の整理、②専門家への相談、③申請準備を段階的に進めると効果的です。
取得を検討している方は、下記のポイントをチェックしてみてください。
事業計画を明確にし、法的な枠組みを検討する
最初のステップは、自社が展開したい決済代行のビジネスモデルを具体的に設計し、事業計画として明確化することです。
どのようなサービスを提供し、どのような顧客層をターゲットとし、いかにして収益を上げていくのか等を詳細に定義します。
その上で、策定したビジネスモデルが資金決済法や割賦販売法、銀行法など、どの法律の規制対象となるのかを法的な枠組みを検討しましょう。
許認可に詳しい弁護士や行政書士に相談する
資金決済法や割賦販売法、銀行法等の法規制は非常に専門的かつ複雑なため、許認可の取得手続きを自社のリソースのみで完結させることは困難な場合があります。
その場合、金融分野の許認可に精通した弁護士や行政書士といった専門家に相談することが有効です。
例えば、弊社(サポート行政書士法人)では、ビジネスモデル関するヒアリング、社内規程等の申請書類の作成、監督官庁との折衝など、過去実績に基づいたサポートを提供しています。
専門的な知見を活用することで、手続き上の不備を防ぎ、審査をスムーズに進めることが可能にできると言えます。
監督官庁への事前相談と申請書類を準備する
実際に申請する前に、事業所の所在地を管轄する監督官庁へ事前相談を行うのが一般的です。
この事前相談の場で、自社のビジネスモデルや事業計画を具体的に説明し、担当官と意見交換をします。
その後、監督官庁からの指摘や助言を踏まえて、申請書類一式の準備を進めることになります。
申請書類には、登録申請書のほか、各種社内規程、チェックリスト、役員の履歴書など、多くの資料が含まれます。
これらの書類は事業の適法性や健全性を証明する根拠となるため、内容に齟齬が生じないよう注意を払って作成することが重要です。
許認可の登録までにかかる期間
必要となる許認可の種類や事業スキームの複雑さにもよりますが、本記事で紹介した決済代行に関する主な許認可では、登録が完了するまで概ね6か月〜1年以上を要するのが一般的です。
これは、監督官庁への事前相談に始まり、申請書類の準備、その後の詳細審査や補正指示への対応、担当官によるヒアリングといった一連のプロセスを経るため、相応の時間が見込まれるためです。
また、登録免許税や各種協会入会に係る費用など、コスト面についても十分に織り込んでおく必要があります。
事業計画の段階で、期間と費用の双方をあらかじめ見積もっておくことが肝要です。
まとめ
決済代行を開始するためには、ビジネスモデルによっては許認可の取得が必要です。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業、資金移動業、電子決済等代行業など、適用される法律や求められる要件は多岐にわたります。
決済代行業者を目指す事業者は、自社のサービスがどの規制に該当するのかを正確に把握し、財産的基礎や業務遂行体制、法令遵守体制といった登録要件を満たしていく必要があります。
本記事のポイントを踏まえつつ、自社のビジネスモデルと適用法令の整合を見直し、安全性と信頼性を備えた決済代行サービスを確立しましょう。
本記事の監修者

サポート行政書士法人 東京本社
主任コンサルタント 清水 侑
保有資格:行政書士、公認AMLスペシャリスト
取扱分野:金融許認可