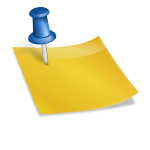第三者型発行者 : 登録申請
更新日:2025年9月2日
前払式支払手段(第三者型)発行者とは
前払式支払手段とは、利用者があらかじめ金銭を支払うことにより、その金銭の価値に応じた商品やサービスの提供を受けられる仕組みをいいます。
代表例はプリペイドカードや電子マネーです。このうち第三者型前払式支払手段とは、自社だけでなく外部の加盟店でも利用できるタイプを指します。
例えば、交通系ICカードや流通系電子マネーなど、発行者以外の多数の店舗で使える仕組みはすべて第三者型に分類されます。
これに対して、自社店舗でしか使えない「自家型」も存在しますが、本記事では第三者型発行者の登録申請について説明します。
発行するためには登録申請が必要
第三者型前払式支払手段を発行したい場合、資金決済法に基づき管轄の財務局への登録をしなければなりません。
登録を受けずに第三者型前払式支払手段を発行すると法令違反となるため、事前の登録申請が必要となります。
登録申請の流れ
登録申請は、大きく分けて「事前相談」「ドラフト審査」「本審査」という三つの段階を経て進められます。
(下記はサポート行政書士法人の実績に基づくものであり、管轄の財務局によっては流れが異なる可能性があります。)
① 事前相談
最初のステップは、財務局や財務事務所との事前相談です。
予定している事業スキームや業務内容について説明し、当局から制度や申請要件に関する確認を受けます。
具体的には、「事前相談整理表」という所定の書式によって確認が行われます。
「事前相談整理表」は約50の質問があり、それらをすべて回答した後でも、より詳細な部分について追加で当局から質問を受けることになります。
② ドラフト審査
事前相談を経た後は、申請書類一式(申請書様式、社内規則、チェックリスト等)のドラフトを作成し、当局と確認を進めます。
この段階はまだ正式な申請ではなく、正式な申請前の当局チェックであり、基本的な社内体制整備に係る事項から細かな誤字脱字まで、様々な指摘を受けることになります。
ドラフト審査を経て、問題がなくなれば、登録免許税(15万円)を納付し、本審査に進むことができます。
(また、任意で日本資金決済業協会等への加入を行います)
③ 本審査
本審査では、ドラフトを踏まえて完成した申請書類を正式に提出(GビズIDを使用した電子申請で行うことが多い)し、当局による審査を受けます。
実務的には、当局からこの段階で細かい確認や補正の依頼が生じることもあります。
標準処理期間が2ヶ月とされており、概ねその期間を経て登録通知が行われます。
その後は、発行保証金の供託等、登録後に必要な手続きを行います。
これらのプロセスにより、正式に「第三者型前払式支払手段発行者」として登録され、業務を開始できるようになります。
登録された事業者は、金融庁HP「前払式支払手段(第三者型)発行者登録一覧」に商号等が掲載されます。
登録要件の概要
前払式支払手段(第三者型)発行者の登録要件の概要は、下記のようになっています。
(1) 組織について
法人、または外国の法人で国内に営業所又は事務所を有するもの
(2) 財産について
純資産が1億円以上であること ※営利を目的としない法人で政令により定めるものは除く
(3) 業務遂行体制について
前払式支払手段により提供される商品またはサービスが公益に反しないための措置が行われていること
加盟店に対する支払を適切に行うための体制の整備が行われていること
(4) 法令順守体制について
前払式支払手段発行業者に関わる法令の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること
(5) 商号について
他の前払式支払手段発行業者(第三者型発行者)が使用している商号・名称同一又は類似のものを用いないこと
(6) 法人またはその役員の拒否要件について
前払式支払手段発行業を営む法人またはその役員が、一定の拒否要件(法令違反、破産手続き等に該当しないこと
業務執行体制と法令順守体制について
「登録要件の概要」のうち、キーポイントは「業務遂行体制について」と「法令順守体制」です。
それら以外は簡潔でわかりやすいのですが、しかし「業務遂行体制について」は「前払式支払手段により提供される商品またはサービスが、公益に反しないための措置が行われていること&加盟店に対する支払を適切に行うための体制の整備が行われていること」、「法令順守体制」は「前払式支払手段発行業者に関わる法令の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること」と、抽象的な定義しか法律では規定されていません。
これは、「法律ではざっくりと決めるから、詳しいことは事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係5.前払式支払手段発行業者関係)を見てね」という理由からです。
この事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係5.前払式支払手段発行業者関係)で決められたルールが膨大な量に上ります。
反社会的勢力による被害の防止、利用者情報管理、システム管理まで、前払式支払手段発行業登録を目指す事業者が超えるハードルは多岐に渡ります。
分量でいうと、ルールが書かれたページだけでもA4用紙で50枚近くに上ります。
参考:事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係5.前払式支払手段発行業者関係)
高額電子移転可能型前払式支払手段について
高額電子移転可能型前払式支払手段を発行したい場合、マネーロンダリング・テロ資金供与対策のための取引時確認、顧客管理、取引モニタリング等の体制も求められます。
どんなものが高額電子移転可能型前払式支払手段に該当するのか等、詳細については下記記事をご確認ください。
登録後の諸手続
前払式支払手段(第三者型)発行者として登録した後、必要な行政手続があります。
ここではそれらの行政手続の中で代表的なものを紹介します。
■発行の業務に関する報告書
第三者型発行者は、「前払式支払手段の発行に関する報告書」を管轄の財務(支)局長等に提出する義務があります。
いつ提出するかというと、各基準日(3月末及び9月末)から2カ月以内なので、5月末及び11月末に提出しなければなりません。
■変更の届出
第三者型発行者は、以下の事項のいずれかに変更があった場合には、 管轄の財務(支)局長等に添付書類と共にその旨を遅滞なく届け出なくてはなりません。
| 変更事項 |
| 氏名、商号又は名称の変更 |
| 資本金又は出資の額 |
| 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止した場合 |
| 役員の変更 |
| 前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等の変更 |
| 物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限の変更 |
| 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法の変更 |
| 前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先の変更 |
| 主要株主の変更 |
| 一般社団法人等が当該預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合 |
| 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 |
お困りの方はサポート行政書士法人へご相談ください
サポート行政書士法人では、新規で許認可を取得されたい方から、既存の事業者の皆様に対して、資金決済法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
資金決済法に関する登録(資金移動業、前払式支払手段発行業等)は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、資金決済法に関する法務サービスを提供します。
初回の面談は無料で承っています。ぜひ相談ください。
この記事の監修者

公認AMLスペシャリスト
清水 侑