行政書士はどんな義務を負っているの?――意外と知らない「行政書士のルール」
投稿日:2025年4月25日

行政書士がどんなルールや義務のもとで活動しているのかは、あまり知られていないのではないでしょうか。
実は、行政書士法という法律のなかで、行政書士がしっかりと守らなければならない義務が定められています。
そのポイントをわかりやすくご紹介します。
事務所は一つだけ!「行政書士事務所」に関するルール
※個人開業の行政書士が開設できる事務所は、原則として1カ所に限られます。法人の場合は別途、法人格に関する規定が適用されます。
- 行政書士は事務所を置かなければならない
行政書士が業務を行うには、どこかに「行政書士事務所」を構えている必要があります。
これは、正式に連絡・相談を受け付ける場所を明らかにするため。 - 事務所は二つ以上はダメ
いくつも事務所を構えて同時に運営してしまうと、どこが主たる拠点なのか不明確になるため、法律で禁止されています。(これは個人で行政書士事業を展開する場合を想定しています) - 使用人の行政書士は独自の事務所を持てない
所属している法人や他事務所を通じて仕事をする立場の場合は、自分専用の事務所を立ち上げられないルールになっています。
どうしてこんな決まりがあるの?
行政書士が「きちんと届出している場所で業務を行っている」という明確な管理が必要だからです。
依頼者にとっては「ここに行けばこの行政書士に相談できる」という安心感につながります。
業務記録や報酬額はどうなっているの?

帳簿の備付・保存義務
行政書士は、受けた事件(案件)の名称や日付、報酬額、依頼者の情報などを帳簿にしっかり記録し、その帳簿と関係書類を最低2年間保存する決まりがあります。
これは後から「どんな内容で依頼を受けたのか」を振り返れるようにするため。また、「報酬金額が不透明…」といったトラブルを防ぐ目的もあります。
報酬の額の掲示(料金表の掲示)
行政書士事務所では、「この業務はいくらかかるか?」を分かりやすく提示するため、報酬額の掲示が義務づけられています。
信用と品位を守る!誠実な業務、守秘義務など
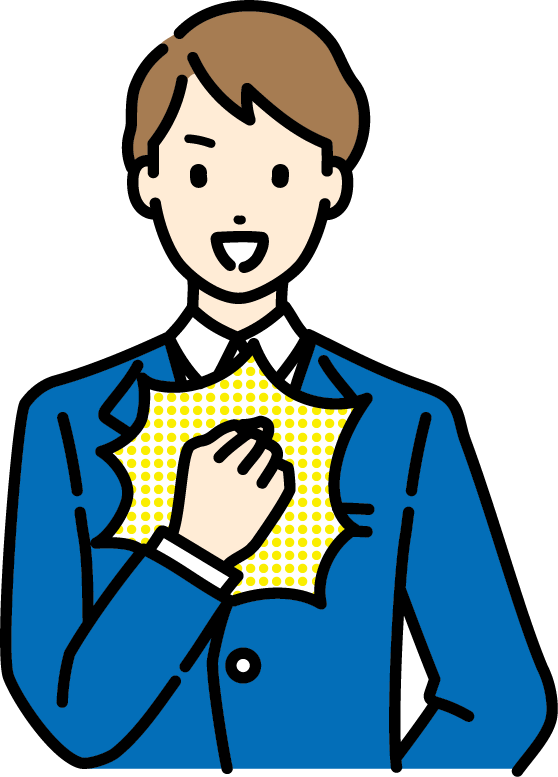
誠実に業務を行い、行政書士の信用や品位を損なう行為はNG
行政書士は、依頼者との信頼関係が欠かせない仕事。
社会的にも公共性の高い職種で、法律で明確に「行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と定められています。
正当な理由がなければ依頼を断れない
「面倒だから断る」というわけにはいきません。
きちんとした理由がないかぎり、依頼を拒むことはできないのです。
秘密を守る義務(守秘義務)
行政書士は、依頼者の個人情報やビジネス上の重要情報を扱うことが多く、これを法律上厳重に守る責任があります。依頼を受けた内容や相談内容は、勝手に外部へ漏らすことがあってはなりません。
行政書士でなくなった後も、同じ義務が続きます。
研修を受けてスキルアップ
行政書士は業務の専門性を維持・向上させるため、自分が所属する行政書士会や日本行政書士会連合会が行う研修に参加し、学び続けるよう努めなければならないとされています。
こうした研修制度によって、新しい法律や手続きの改正などに対応し、常に最新の知識を吸収できる仕組みになっているのです。
(著者:徐)

