特定技能制度改正!在留期間3年が可能に
投稿日:2025年10月27日
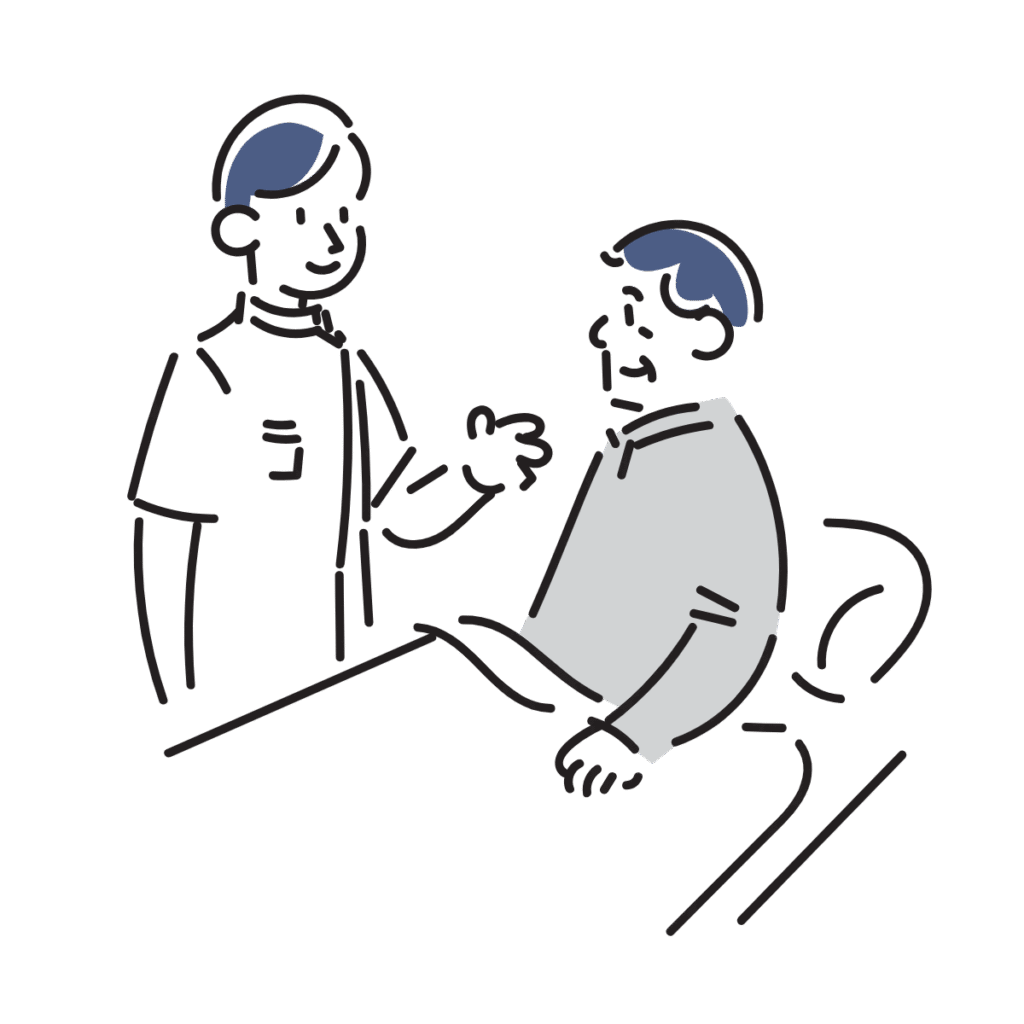


出入国在留管理庁は、特定技能外国人受入れに関する運用要領を2025年9月30日付及び10月17日付で改正しました。今回の改正により、特定技能1号での在留期間は従来の「1年以内」から「3年以内」に拡大され、中長期での受入れがしやすくなっています。
ポイント1:通算在留期間
- 基本上限:
3年→5年 - 休業期間はカウント除外:「産前産後休業」「育児休業」「病気・怪我による長期休業」
- 例外ケース:特定技能2号移行を目指すも不合格の場合、最大6年まで延長可能
ポイント2:雇用契約書作成上の注意
在留カードで「3年」を取得する場合、申請・契約書上で以下の点を意識する必要があります。
- 「日本での活動予定期間」を3年以上(可能なら5年程度)に設定
- 雇用契約書の契約期間も3年以上とすることが望ましい
ただし、契約期間を長く設定することには企業側リスクもあります。
従業員の実力や勤務態度によって契約解除が難しくなる場合があるため、
メリット・デメリットを整理したうえで契約期間を決定するプロセスが重要です。
さらに、長期雇用を前提とする場合は以下も確認してください。
- 以前に特定技能1号として在留していた期間の有無(通算期間に影響)
- 産前・産後・育児・病気休業など、在留期間カウント外となる期間への対応
- 支援計画や受入企業・登録支援機関の適格性、届出義務、法令遵守状況の整備
ポイント3:契約期間設定におけるメリット・デメリット
メリット
- 在留期間「3年」が付与されれば、更新手続きの頻度を減らせるため、企業・本人双方の手間・コストが軽減
- 中長期での人材活用が可能となり、教育・育成計画の設計が立てやすい
デメリット
- 契約期間を長めに設定すると、途中での雇用解除・契約終了が難しくなる可能性
- 在留期間・契約期間と勤務状況に齟齬があると、在留許可や更新時にトラブルとなる可能性
- 通算在留期間(5年)が近づくと、次のステップ(特定技能2号移行)を視野に入れた体制が整っていないと、
人材確保の継続が難しくなるリスク
今回の改正により、特定技能人材の中長期受入れがよりスムーズになります。契約期間設定や休業期間の取扱いを含め、実務上の整備を早めに確認することがポイントです。
弊社では、貴社の状況に応じて最適な契約期間・申請手続きの提案を行い、在留期間3年の取得や更新サポートを実施します。
(参考:https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html)
(執筆者:リョウ)
« 前の記事へ

