【不動産特定共同事業法】不動産特定共同事業許可とは
更新日:2025年9月5日
◆もくじ◆
- 1 不動産特定共同事業とは?
- 2 不動産特定共同事業の許可について
- 3 2019年の法改正について
- 4 申請
- 5 不動産特定共同事業許可の要件
- 6 不動産特定共同事業の「変更認可」と「変更届」
- 7 不動産特定共同事業者の業務運営
- 7.1 投機的取引の抑制(不動産特定共同事業法第14条第2項)
- 7.2 標識の掲示(不動産特定共同事業法第16条第1項)
- 7.3 広告の規制(不動産特定共同事業法第18条)
- 7.4 不当な勧誘行為等の禁止①(不動産特定共同事業法第20条、第21条、第21条の2及び第22条)
- 7.5 不当な勧誘行為等の禁止②
- 7.6 約款に基づく契約の締結(不動産特定共同事業法第23条)
- 7.7 不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付(不動産特定共同事業法第24条第1項)
- 7.8 情報通信の技術を利用した提供(不動産特定共同事業法第24条第3項)
- 7.9 不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付(不動産特定共同事業法第25条 第1項)
- 8 関連記事
- 9 不特法のご相談はサポート行政書士法人へ
不動産特定共同事業とは?
不動産特定共同事業とは、複数の投資家から出資を受け、その出資を基に現物の不動産の取得等を行い、その運用(賃貸等)により得られた収益の一部を投資家に分配する事業のことを指します。上記に基づく不動産特定共同事業者と投資家間の契約を不動産特定共同事業契約といい、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介を行うことも不動産特定共同事業に該当します。
不動産特定共同事業を行うためには、不動産特定共同事業法第3条第1項に定める許可又は第41条第1項に定める登録を受けなければなりません。
不動産特定共同事業者として許可を受けると、下記の一覧に事業者名が記載されることになります。
→ 不動産特定共同事業法に基づく事業者及び適格特例投資家一覧
契約類型
不動産特定共同事業法第2条第3項各号に不動産特定共同事業契約として一定の契約類型が定められています。
当該条文では、「任意組合契約型(同項第1号に該当)」、「匿名組合契約型(同項第2号に該当)」、「賃貸型(同項第3号に該当)」の3つの契約類型が定められています。
【任意組合契約型】
事業者及び各投資家が出資をして、対象不動産の運用を共同の事業として営む任意組合を組成。
事業者が業務執行組合員として対象不動産を運用し、各組合員(投資家)に収益の分配を行う。
【匿名組合契約型】
事業者が営業者となり、投資家が匿名組合員となって営業者の行う事業に出資をする契約を締結。
営業者は匿名組合事業として対象不動産を運用し、各投資家に収益の分配を行う。
【賃貸委任契約型】
対象不動産を共有する事業者と各投資家との間で、投資家がその共有に属する対象不動産を事業者に賃貸又は賃貸の委任をする契約を締結。
事業者が対象不動産を運用し、各共有者(投資家)に収益の分配を行う。
小規模不動産特定共同事業とは
不動産特定共同事業のうち、投資家一人あたりの出資額が原則として100万円を超えず、さらに投資家全体からの出資総額が1億円を超えない場合には、小規模不動産特定共同事業として登録を受けたうえで、事業を行うことが可能です。
適格特例投資家限定事業とは
不動産特定共同事業を適格特例投資家に限定して行う場合、適格特例投資家限定事業として届出を行うことにより、事業を行うことが可能です。
不動産特定共同事業の許可について
許可の種別
不動産特定共同事業法第2条第4項各号に、不動産特定共同事業の許可の種別が規定されています。
| 第1号事業者 | 投資家との間で不動産特定共同事業契約を締結して、当該契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益等の分配を行う事業 |
| 第2号事業者 | 不動産特定共同事業契約の締結の代理または媒介を行う事業(第1号事業の代理・媒介) |
| 第3号事業者 | 特例事業者より委託を受けて、当該特例事業者が投資家との間で締結した不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う事業 |
| 第4号事業者 | 特例事業者が当事者となり投資家との間で行う不動産特定共同事業契約の締結の代理・媒介をする行為 |
2019年の法改正について
2019年の不動産特定共同事業法改正は、主に不動産クラウドファンディングの活性化と投資家保護の強化に重点が置かれました。
不動産特定共同事業法改正によって、今まで信託受益権化が出来なかった不動産を投資対象にすることが出来るようになりました。
さらに倒産隔離SPC(特別目的会社)が認められ、資金が集めやすくなりました。
本改正には、少しでも多くの民間資金を日本全国の不動産のバリューアップや再生・開発に振り向けたいという狙いがあります。
主なポイント
- 倒産隔離SPC(特別目的会社)が認められるようになりました。
- 現物不動産への投資スキームが組めるようになりました。
- 3号業者、4号業者が新設されました。
不動産特定共同事業法改正の1番のポイントは、倒産隔離された特別目的会社(SPC)が認められ、現物不動産への投資スキームを組めるようになったことです。
これによって地方の物件や老朽化した物件など、今まで投資対象になりえなかった物件にも投資ができるようになったので、今後の日本の不動産業界の活性化につながるということです。
さらに、3号業者、4号業者が新設されたことによって、これまで不動産特定共同事業取扱業者として認められていなかった地方のデベロッパーなどが新たに認められることになります。
欧米では倒産隔離SPC(特別目的会社)の考え方が常識でした。
しかし、日本では不動産特定共同事業法によって、たとえ「器」に過ぎない会社であっても投資家から資金を集め、不動産を保有する以上、許可が必要となっていました。
許可をとるのにコストがかかることから、不動産特定共同事業法の規制を回避する方法として不動産の信託受益権化が進んでいました。
しかし、この方法を用いると日本に多く存在する老朽化、遊休化した不動産へ投資することができませんでした。
今回の不動産特定共同事業法改正に伴い、今まで投資対象になかった不動産を再生させ、地域経済の活性化や資産デフレからの脱却を図るメリットが期待されています。
申請
申請は、事業の種類、事務所がいくつあるか(複数の都道府県)によって申請先が異なります。
第1号・第2号事業者かつ事務所が1都道府県のみにある場合は、当該都道府県が申請先になります。 都道府県によって申請方法や必要書類が異なりますので、該当する都道府県に問い合わせが必要です。
第3号・第4号事業者又は第1号・第2号事業者かつ事務所が複数都道府県にまたがる場合は国交省(金融庁)が申請先になります。
不動産特定共同事業許可の要件
許可の基準
不動産特定共同事業の許可には、法律や政令、国交省のガイドライン等で基準が定められています。しかし、人的構成や財産的基礎に関する細かい判断は許可権者に委ねられる部分が大きく、「ある都道府県では認められたが、別の都道府県では認められない」といった事例も少なくありません。このため、経験豊富な行政書士に依頼することは、事業者にとって大きな意味があります。
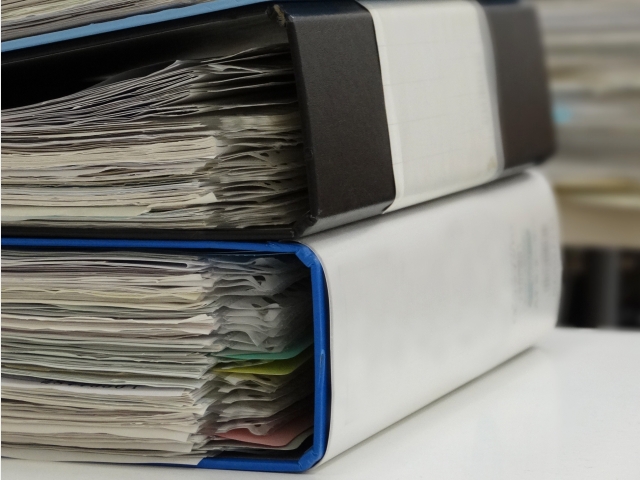
第1号~第4号事業者の共通要件
| 主な共通要件 | ・宅地建物取引業者免許を有する法人 ・事務所ごとの業務管理者(※)の設置 ・公正かつ適確に業務遂行ができる人的構成 ・財産及び損益の状況が良好かつ良好に推移する見込み ・会計監査を受けた財務諸表の提出(直近3年分) ・不動産特定共同事業契約約款の政令で定める基準への適合性 など |
※業務管理者になるためには・・・
宅地建物取引士資格+法定の資格(不動産コンサルティングマスター・ビル経営管理士・不動産証券化協会認定(ARES)マスターなど)を保有していることが必要です。その他、宅地建物取引士資格+不動産特定共同事業に関する3年以上の実務経験という要件もありますが、新規許可申請の場合は難しいです。
許可の種別によって異なる要件
| 種別ごとの要件 | ・資本金 1号:1億円、2号:1,000万円、3号:5,000万円、4号:1,000万円 ・第二種金融商品取引業登録があること(4号のみ) |
不動産特定共同事業の「変更認可」と「変更届」
不動産特定共同事業における変更認可と変更届は異なる手続きです。
変更認可は、一定の重要な変更について事前に認可を受ける手続きです。
不動産特定共同事業において、事業の根本的な部分に関わる変更を行う場合には、事前に認可を得る必要があります。
一方、変更届は、不動産特定共同事業者が一定の事項を変更した際に、事後的に届け出る手続きです。
一般的に、事業者の名称変更、住所変更、役員の変更などの比較的軽微な変更が対象になります。

不動産特定共同事業の変更認可
- 不動産特定共同事業の種別を変更するとき
- 不動産特定共同事業約款の作成、もしくは変更をしようとするとき
- 新たに電子取引業務を行おうとするとき
- 事務所を追加設置するとき
これらの場合は変更認可を受けなければなりません。
ただし、単に字句を修正するなどといった軽微な変更については、変更の認可は不要です。
変更認可は、変更事項に問題がないか事前審査が行われ、内容に問題がなければ変更の本申請を行います。
申請に不透明な箇所が見受けられた場合には面談が行われることもあります。
変更認可申請の注意点
内容に変更があり、申請する場合、次のことに注意が必要です。
- 不動産特定共同事業の種別を変更する場合にあっては、当該変更後法第7条第1号及び第6号に規定する許可の基準を満たしていること。
- 新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をする場合にあっては、当該変更後法第7条第5号に規定する許可の基準に適合していること。
不動産特定共同事業の変更届
資本金の増資や減少、役員の変更など会社の組織体制が変更した場合、変更届の提出が必要になります。
基本的に事前審査や面談は行われず、必要書類を用意して管轄行政へ提出します。
が外国にある場合であっても、法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約から除外されません。
不動産特定共同事業者の業務運営
不動産特定共同事業法第14条、第16条第1項、第18条、第20条、第21条、第21条の2、第22条、第23条、第24条第1項及び第3項、第25条第1項、第31条の2及び第65条の規定等に係る監督に当たっては、投資家保護の観点から、次に掲げる事項に留意する必要があります。
投機的取引の抑制(不動産特定共同事業法第14条第2項)
例えば、不動産特定共同事業者等が地価の上昇による転売益のみを目的として対象不動産を短期的に売却する行為は、行ってはいけません。これに違反した場合、不動産特定共同事業法第34条又は第35条に規定する指示又は業務停止命令の対象となりうることがあります。
標識の掲示(不動産特定共同事業法第16条第1項)
不動産特定共同事業法第16条第1項に規定する「公衆の見やすい場所」とは、事務所の内外を問わず事業参加者が容易に見ることができる場所のことをさします。材質については、金属等長期の使用に耐え得るものを用いなくてはいけません。
広告の規制(不動産特定共同事業法第18条)
不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者が行う広告の表示は、投資家への投資勧誘の導入部分に当たり、明瞭かつ正確な表示による情報提供が適正な投資勧誘の履行を確保する観点から最も重要ですが、その徹底に当たっては、以下の点に特に注意してください。
(1) 申込者の判断に影響を及ぼすこととなる重要事項に関する留意事項
- 申込者が支払うべき手数料、報酬、その他の対価又は費用が無料又は実際のものよりも著しく低額であるかのように誤解させるような表示をしていないか。
- 許可申請書に記載した商号又は名称と異なるもの を用いた表示をしていないか。等
(2) 明瞭かつ正確な表示
- 取引の長所に係る表示のみを強調し、短所に係る表示が目立ちにくい表示を行っていないか。等
(3) 誇大広告に関する留意事項
- 不動産特定共同事業に係る不動産取引により確実に利益を得られるかのように誤解させて、投資意欲を不当に刺激するような表示をしていないか。等
不当な勧誘行為等の禁止①(不動産特定共同事業法第20条、第21条、第21条の2及び第22条)
不動産特定共同事業法第20条、第21条、第21条の2及び第22条並びに規則第38条により不当な勧誘等に該当するか、以下のような禁止行為が該当します。
- 社会的に過剰な営業活動であると批判を浴びるような勧誘をする行為
- 不動産の空室リスク等を投資家に負わせないよう、一括転貸 借契約、保証契約その他により、信用補完措置が適正になされ ている場合において、その根拠を示し予想利回りを表示する行為 等
不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者は、第21条の2で準用する金融商品取引法第40条の規定に基づき、投資家の知識、経験、財産の状況、 投資目的やリスク管理判断能力等に応じた取引内容や取引条件に留意し、投資家属性等に即した適正な投資勧誘の履行を確保する必要があります。
そのため、投資家の属性等及び取引実態を的確に把握し得る投資家の管理態勢を確立することが重要であり、例えば以下のような点に気を付けてください。特にインターネット取引については細心の注意が必要です。
- 投資家属性等の的確な把握及び投資家情報の管理の徹底
投資家の投資意向、投資経験等の投資家属性等を適時適切に把握するため、投資目的・意向を十分確認し、当該投資目的・意向を不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同 事業者と投資家の双方で共有できているか。また、投資家の申出に基づき、投資家の投資目的・意向が変化したことを把握した場合には、変更後の内容を不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者と投資家の双方で共有するなど、 投資勧誘に当たっては、当該投資家属性等に即した適正な勧誘に努めるよう役職員に徹底しているか。 等
不当な勧誘行為等の禁止②
さらに、高齢の投資家は、過去の投資経験が十分であったとしても、身体的な衰えに加え、短期的に投資判断能力が変化する場合もあることから高齢の投資家に対する投資勧誘においては、適合性の原則に基づいて、慎重な勧誘・販売態勢を確保するとともに、問題のある勧誘・販売を早期に発見するためのモニタリング態勢を整備する必要があります。また、商品販売後においても、丁寧にフォローアップしていく必要がります。
以上を踏まえ、以下の点に気を付けてください。
- 商品の販売後においても、高齢の投資家の立場に立ってきめ細かく相談にのり、投資判断をサポートするなど丁寧なフォローアップを行っているか。 等
約款に基づく契約の締結(不動産特定共同事業法第23条)
- 不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は特例事業者が締結する不動産特定共同事業契約は、不動産特定共同事業第3条第1項の許可、第9条第1項の認可、第42条第1項の登録又は第 46条第1項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて締結する必要があるものの、必ずしも不動産特定共同事業契約約款と一字一句同一の文言の契約である必要はなく、不動産特定共同事業契約において字句を修正する程度のものは第23条に違反するものではありません。
- 不動産特定共同事業法施行規則第14条又は第65条に規定する軽微な追加又は変更に該当する事項についての不動産特定共同事業契約約款の変更については、法第9条第1項の認可又は法第46条第1項の変更登録を受ける必要はありません。
不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付(不動産特定共同事業法第24条第1項)
第24条第1項の規定により交付される不動産特定共同事業契約の成立前の書面において、不動産特定共同事業法施行規則第43条第1項に規定する事項が記載されていること、また、以下の点注意して交付してください。
- 特例事業の場合、不動産特定共同事業法施行規則第43条第1項第11号に規定する「不動産特定共同事業契約の法第2条第3項各号に掲げる契約の種別及び当該種別に応じた不動産特定共同事業の仕組み」には、不動産特定共同事業契約の締結の相手方が不動産特定共同事業者ではなく特例事業者であること、特例事業者が不動産特定共同事業法第4条第1号に掲げる行為を専ら行うことを目的とする法人であること等が記載されていること。
- 不動産特定共同事業法施行規則第43条第1項第31号に規定する「損失発生要因に関する事項」は、空室の発生、賃料の下落、対象不動産の評価額の下落等により元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨を含むこと。なお、不動産特定共同事業法第2条第3項第3号に規定する不動産特定共同事業契約については、安定した事業の継続又は円滑な事業の終了を確保するための措置の有無及びその内容が記載されていること。 等
情報通信の技術を利用した提供(不動産特定共同事業法第24条第3項)
令第8条第1項に規定する承諾については、あらかじめ包括的に承諾を得ることも可能ですが、その際には、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示す必要があります。交付される不動産特定共同事業契約の成立前の書面が電磁的方法により提供される場合には、投資家がその操作する電子計算機の画面上に表示される説明事項を読み、その内容を理解した上で画面上のボタンをクリックする等の方法で、投資家が理解した旨を確認することにより、規定する説明を行ったものとみなされます。
不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付(不動産特定共同事業法第25条 第1項)
交付される不動産特定共同事業契約の成立時の書面において、法第25条第1項及び規則第47条に規定する事項が記載されている必要があります。第四号事業を行う不動産特定共同事業者が法第25条第1項の規定により交付する不動産特定共同事業契約の成立時の書面においては、当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を委託された不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)又は小規模不動産特定共同事業者(小規模第二号事業を行う者に限る。)に係る法第25条第1項及び規則第47条に規定する事項も記載されていることが必要です。
関連記事
不特法のご相談はサポート行政書士法人へ
- 新しく1・2号事業者許可をしたい
- 3号許可を取りたいが、当社で取得できそうか
- 許可取得後の、実務アドバイスを依頼したい
以上のような問い合わせを、無料相談でよくいただきます。
弊社では、日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を駆使して依頼者の皆様のスムーズなスタートアップをフルサポートいたします。
新規事業・許認可事業のパートナーとしてぜひサポート行政書士法人をご活用ください。




